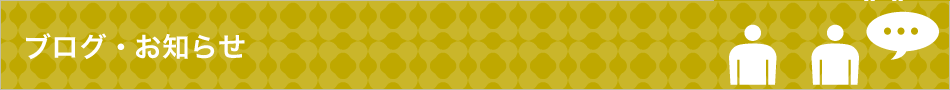- [2025.04.02]
- 会社が従業員に食事を支給したとき
会社が役員や使用人に食事を支給した場合、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与課税されません。
①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
②「食事の価額-役員や使用人の負担額」が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること
もしこれらの要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担した額を控除した残額が、給与として扱われます。
【食事の価額とは】
①弁当などを購入して支給する場合は、業者に支払う金額
②社員食堂などで会社が作った食事を支給する場合は、材料費など食事を作るために直接かかった費用の合計額
※食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合は、一部例外を除き補助する全額が給与として扱われます。
※残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として扱わなくてもよいことになっています。
- [2024.12.05]
- 今年の年末調整では、定額減税に注意!
ようやく少し寒くなってきました。
インフルエンザやら悪いものも流行ってるようなので、気をつけて12月を乗り切りたいところです。
はやいもので年末調整の時期も近づいてきています。
今年はなんといっても定額減税が厄介ではないでしょうか。
とにもかくにも、まずは従業員さん全員の定額減税対象額を確定しておかなければなりません。
世の中けっこう計算間違いが出そうですね・・・
今年だけの話ですし・・・
と、愚痴ってても仕方ないので、
例年より気をつけて年末調整を行いましょう!
- [2024.11.25]
- 給与所得者でも確定申告が必要な場合
気が付けば令和6年もあと1か月ちょっとです。
令和7年2月17日(月)から3月17日(月)は、令和6年分の所得税確定申告の期間です。
年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者は年末調整を行うため原則として確定申告は不要ですが、医療費控除や雑損控除を適用して所得税の還付を受ける場合には確定申告が必要です。
また、次のような給与以外の収入がある人は確定申告が必要になります。
① 生命保険等の満期保険金
生命保険会社等から受け取った満期保険金や解約返戻金は、一時所得として確定申告が必要な場合があります。
なお、生命保険契約等の契約者(保険料負担者)と保険金の受取人が同一でないときは、贈与税の課税対象となります。
② ふるさと納税の返礼品
ふるさと納税の返礼品の受取は、一時所得に該当します(寄付額の30%が目安)。返礼品以外に、満期保険金等の他の一時所得があった場合、合計して年間50万円を超えるときは確定申告が必要になります。
③ 上場株式等の譲渡や配当による収入
「源泉徴収なしの特定口座」における譲渡による収益が20万円超である場合は、確定申告が必要です。
「源泉徴収ありの特定口座」は、原則として確定申告は不要ですが、複数の証券会社の口座において損益通算をする場合や、損失を3年間繰り越せる繰越控除を適用する場合は、確定申告が必要です。
④FX(外国為替証拠金取引)や暗号資産取引により得た収益については、確定申告が必要な場合があります。
その他、確定申告が必要な場合については、以下の国税庁Webサイト「確定申告が必要な方」を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm
- [2024.06.19]
- 相続土地国庫帰属制度の運用状況
税理士の檜山です。
昨年4月からスタートした相続土地国庫帰属制度。
相続はしたものの土地の管理ができない・遠くにあるため利用する予定がないなど、土地を手放したいというニーズに応えるために創設された制度です。
目的へのアプローチはいいのですが、国庫帰属までのハードルが高く私の周りで申請したという話はあまり聞いていません。
制度開始から1年を経過したこともあり、法務省から現時点の統計データが公表されました。
(以下、令和6年5月31日現在の数値です)
申請件数 2207件
地目別
田・畑 837件(38%)
宅地 793件(36%)
山林 338件(15%)
その他 239件(11%)
帰属件数 460件(20.8%)
地目別
田・畑 137件(16.3%)
宅地 190件(24.0%)
山林 16件( 4.7%)
その他 117件(49.0%)
審査中の数が結構あるのかもしれませんが、帰属件数は20%(5件に1件)の割合です。
地目ごとに見てみると、相続人が活用に困る傾向にある田・畑は6件に1件、山林は20件に1件の割合です。
国も帰属後の活用を考慮してハードルを厳しくしていると思いますが、個人的にはもう少し要件の緩和をしてほしいところです。
- [2024.05.23]
- 【インボイス制度】 少額特例
令和5年10月よりインボイス制度がスタートし、事務処理等の混乱も少し落ち着いてきたと思いますが、【少額特例】のおさらい。
『一定規模以下の事業者』は、インボイス制度開始から『6年間』、『税込1万円未満』の課税仕入について、『インボイスの保存がなくても』、帳簿のみで『仕入税額控除が可能』。
注)一定規模以下の事業者とは・・・
①基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1億円以下
又は、
②特定期間(個人の場合は前年の1月から6月の期間、法人の場合は前事業年度開始の日から6月の期間)の課税売上高 が5千万円以下
今一度検討すると、この少額特例が適用できて事務負担を減らすことができるかもしれません。
- [2023.09.29]
- インボイス制度開始後のETCに係る書類の保存
いよいよ10月1日からインボイス制度が開始します。
世の中まだまだ混乱している中ですが、今回はETCを利用した高速道路利用料金について、現時点での書類保存要件について記載します。
※前提として、支払った料金について仕入税額控除を受けたい場合に限ります。
①クレジットカード会社が交付する利用明細書は、適格請求書には該当しない。
一定期間の高速道路の利用日・区間・金額がズラッと記載されているこれまでもお馴染みの明細書です。これは適格請求書には該当しないということなので、これだけを保存していてもダメです。
②高速道路会社が運営するホームページから、適格簡易請求書に該当する「利用証明書」をダウンロードして保存する必要がある。
これが手間だなと感じていました。ただ、以下③に記載する方法でも良いと公開されています。
③利用証明書は毎月保存する必要はなく、利用する高速道路会社ごとに、10月1日以後一回のみ保存すればOK
例えばAとBが運営する高速道路の料金をETCで支払っている場合、10月1日以後のAとBそれぞれの利用証明書を一回だけ保存し、あとはクレジットカード会社が交付するいつもの利用明細書を保存しておけば良い、ということになります。
- [2023.06.05]
- 便器の勘定科目
トイレの便器の交換、時々あると思います。
内容や金額によっては「修繕費」として処理する場合もあると思いますが、
固定資産に計上する場合はどうなるのでしょうか?
建物付属設備の中に「給排水設備」というものがあり、これに該当すると考えられます。
そうすると・・・
勘定科目は「建物附属設備」で耐用年数は「15年」となります。
※ただし、1単位あたり20万円未満であれば「一括償却資産」として処理できる場合もあります。
- [2022.12.08]
- 令和5年分扶養控除等申告書
令和4年も終わりが近づき、年末調整の時期が近づいてきました。
今回は年末調整の時に勤務先へ提出することの多い「扶養控除等申告書」の令和5年分を確認します。
①「非居住者である親族」欄の追加
国外居住者を扶養控除の対象とする場合、令和5年からは一定の要件に該当する親族のみが対象となるため、要件をクリアしているか確認する欄が追加されました。
控除対象となるのは、16歳以上30歳未満、70歳以上、または30歳以上70歳未満の者で留学生・障害者・38万円以上の送金を受けている者、となります。
なお、確認書類の提出も必要となるので要注意です。
②「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の追加
控除対象となる配偶者や扶養親族の中で、退職所得が見込まれる人がいる場合は記入します。
年々記入事項が増えたり分かりにくくなっている年末調整関連書類ですが、必要事項を書き忘れたりすると思わぬ損をすることも考えられます。
よくよく注意して提出しましょう!
- [2022.06.08]
- 雇用調整助成金(新型コロナウィルスの特例)、令和4年9月末まで延長
令和4年6月末までとされていた「雇用調整助成金の新型コロナウィルス対策特例措置」が、令和4年9月末まで延長となることが決まったようです。
少しずつ人の流れや売上が戻ってきているかもしれませんが、まだまだ以前のようには戻っていないケースが多いのではないでしょうか。
雇用調整助成金を7月以降も検討する場合は要注意です。
なお、同じく6月末までとされていた休業支援金等、雇用調整助成金以外にも同じく延長となるものがありますので、そちらも併せて要注意です。
- [2022.06.01]
- 農協特例
インボイス制度に関する話題です。
当事務所のブログにもこれまで度々ご紹介しております。
詳しい内容は過去記事をご覧ください。
先日、「免税事業者である漁師は、インボイスが始まるとどうなるんじゃ?」と問い合わせをいただきました。
インボイス、直訳すると「送り状」とか「仕切り書」という意味です。船荷証券のようなものです。消費税法ではこれを「適格請求書」と呼びます。
では、何が記載されるのか?それは商取引の内容とそれに伴う消費税が記載されます。
その記載された消費税の額をもとに、国に納める消費税額を計算します。インボイスがなければ消費税の計算ができなくなります。
このインボイス(適格請求書)を発行できるのは課税事業者かつ適格請求書発行事業者として、国に登録された事業者だけです。
さて、今回の漁師さん。インボイスを発行できるのでしょうか?答えはNOです。
発行するためにはまず、課税事業者になり(売上が年1000万円未満でも届出をすれば課税事業者になれます。当然、毎年確定申告をして消費税を納めることになります)、適格請求書発行事業者として国に登録しなければなりません。
と、いうことは課税事業者にならなければいけないのか?一概にそうは言えません。
漁師さんや農家の方が、漁業協同組合、農業協同組合、卸売市場へ出荷されている場合はインボイスの発行は一定条件のもと免除されています。(※ 委託販売方式、共同計算方式等条件があります。詳しくは市場や農協、漁協等にご確認ください)
また、事業者ではない、一般消費者にのみ販売されている場合もインボイスは必要ありません。(消費税の計算はしませんので)
取引形態は様々と思います。個別にご相談いただければと存じます。 (大 嶋)
- 2025年4月(1)
- 2025年1月(1)
- 2024年12月(4)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(4)
- 2024年9月(3)
- 2024年8月(4)
- 2024年7月(3)
- 2024年6月(2)
- 2024年5月(3)
- 2024年4月(3)
- 2023年12月(4)
- 2023年11月(3)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(2)
- 2023年8月(4)
- 2023年7月(3)
- 2023年6月(3)
- 2023年5月(3)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(1)
- 2023年1月(1)
- 2022年12月(5)
- 2022年11月(3)
- 2022年10月(2)
- 2022年9月(2)
- 2022年8月(4)
- 2022年7月(5)
- 2022年6月(4)
- 2022年5月(3)
- 2022年4月(2)
- 2022年3月(1)
- 2022年1月(3)
- 2021年12月(4)
- 2021年11月(2)
- 2021年10月(4)
- 2021年9月(2)
- 2021年8月(5)
- 2021年7月(2)
- 2021年6月(4)
- 2021年5月(3)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(1)
- 2020年12月(4)
- 2020年11月(2)
- 2020年10月(1)
- 2020年9月(3)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(4)
- 2020年5月(4)
- 2020年4月(2)
- 2020年3月(1)
- 2020年2月(1)
- 2020年1月(3)
- 2019年12月(5)
- 2019年11月(2)
- 2019年10月(3)
- 2019年9月(5)
- 2019年8月(4)
- 2019年7月(3)
- 2019年6月(3)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(4)
- 2019年3月(1)
- 2019年2月(1)
- 2019年1月(1)
- 2018年12月(3)
- 2018年11月(2)
- 2018年10月(4)
- 2018年9月(2)
- 2018年8月(5)
- 2018年7月(4)
- 2018年6月(6)
- 2018年5月(2)
- 2018年4月(2)
- 2018年3月(1)
- 2018年2月(1)
- 2018年1月(4)
- 2017年12月(3)
- 2017年11月(2)
- 2017年10月(2)
- 2017年9月(3)
- 2017年8月(2)
- 2017年7月(2)
- 2017年6月(2)
- 2017年5月(2)
- 2017年4月(2)
- 2017年3月(2)
- 2017年2月(2)
- 2017年1月(2)
- 2016年12月(4)
- 2016年11月(2)
- 2016年10月(2)
- 2016年9月(2)
- 2016年8月(4)
- 2016年7月(2)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(1)
- 2016年3月(1)
- 2016年2月(1)
- 2016年1月(2)
- 2015年11月(3)
- 2015年10月(3)
- 2015年9月(3)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(2)
- 2015年6月(4)
- 2015年5月(2)
- 2015年4月(3)
- 2015年3月(2)
- 2015年2月(2)
- 2015年1月(4)
- 2014年12月(3)
- 2014年11月(1)
- 2014年10月(3)
- 2014年9月(2)
- 2014年8月(3)
- 2014年7月(1)
- 2014年6月(2)
- 2014年5月(1)
- 2014年4月(2)
- 2014年3月(3)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(1)
- 2013年12月(2)
- 2013年11月(3)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(7)
- 2013年7月(9)
- 2013年6月(6)
- 2013年5月(4)
- 2013年4月(5)
- 2013年3月(7)
- 2013年2月(2)
- 2013年1月(4)
- 2012年12月(4)
- 2012年11月(5)
- 2012年10月(8)
- 2012年9月(8)
- 2012年8月(4)
- 2012年7月(6)
- 2012年6月(2)
- 2012年5月(1)
- 2012年4月(1)
- 2012年3月(2)
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(1)
- 2011年12月(1)
- 2011年11月(1)
- 2011年10月(1)
- 2011年8月(2)
- 2011年1月(1)
- 2010年11月(1)