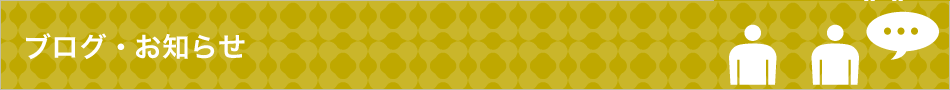- [2022.01.12]
- 仮想通貨の確定申告
税理士の檜山です。
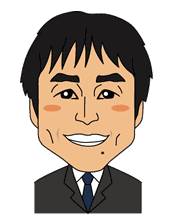
昨年の秋、関東で仮想通貨取引者に対し大規模な税務調査が行われ数十人が約14億円の申告漏れが指摘されました。中国地方でも税務署から無申告の者に対し仮想通貨取引についてのお尋ねが多数送られてきたようです。
令和3年からは、国内の取引所は一定の利益があった顧客に係る支払調書を税務署に提出する義務が課されることとなっていますので、申告もれの発見がより容易になったといえます。
仮想通貨の取引で生じた利益は、雑所得として所得税の課税対象となります。仮想通貨を日本円に換金したときだけでなく、ビットコインでイーサリアムを買うなど仮想通貨で仮想通貨を購入する場合にも、利益は認識されます。
国内の取引所で売買をしている場合は、年間報告書として1年間の取引を比較的容易に把握することができます。海外の取引所で売買をしている場合は、エクセルを駆使したりウェブの計算サイトを活用しないと難しいでしょう。
また、DefiやNFTといった取引について生じた利益に対しても税金対象となるので注意が必要です。
仮想通貨の計算期間は、他の所得と同様に1月1日から12月31日までです。1月から3月半ばまでの間に税額を計算し、口座振替を選択している場合4月20日ごろに納税となります。当然、税金は日本円での納付です。
12月末から納付の4か月弱の間で、仮想通貨の価値が大きく下がった場合は納税資金が不足する恐れがあります。
昨年大きく利益が出ている方は納税額の見込みを早めに計算し、税金相当額を日本円に換金しておくことを強くお勧めいたします。
- [2021.11.12]
- 【インボイス】適格請求書発行事業者の登録申請受付開始!
令和3年10月1日から受付開始しています。
ただし、必ず登録申請した方が良いというわけではないので、事前によくよく検討した方が良いと思います。
インボイス制度がスタートするのは令和5年10月1日からで、登録をこの日に間に合わせるためには原則令和5年3月31日までに申請しなければなりません。
また、登録すれば準備完了ということでもなく、適格請求書の発行などのための準備も併せて必要になります。適格請求書には決まった様式はないとのことですので、記載が必要とされる事項が漏れないようにすれば、エクセルや手書きでも大丈夫です。
登録するにせよしないにせよ、直前にバタバタしないように今から検討・準備したほうが安心です。
よつば会計
中田裕介
- [2021.10.12]
- ふるさと納税の申告手続きが簡素化されます
令和3年の確定申告からふるさと納税の手続きが簡素化されます。
これまで、ふるさと納税については確定申告時に寄付ごとに「寄付金受領証明書」が必要でした。これは、寄付先の自治体が発行するもので、何十か所にふるさと納税をしたときには何十枚もの証明書が送られてきて、管理するのが大変です。
令和3年分の確定申告からは、特定事業者(国税庁指定のふるさと納税サイト)ごとに発行される「寄付金控除に関する証明書」があれば手続きできるようになります。何十か所にふるさと納税をしていても1つのふるさと納税サイトを使っていれば、証明書は1枚で手続きできるようになります。
また、特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法や、国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み添付して申告する方法によって確定申告を行うことができます。
複数の自治体にふるさと納税をしている方は、確定申告時の計算が少し楽になると思います。
詳しい内容は、以下の国税庁ホームページを参照ください。特定事業者として指定されているふるさと納税サイトについても一覧が載っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm
※令和3年10月12日時点の法令に基づき掲載しております。
- [2021.09.28]
- ダイレクト納付・地方税共通納税システム
税金の納付方法の一つに、国税は「ダイレクト納付」・地方税は「地方税共通納税システム」というものがあります。
・ダイレクト納付・地方税共通納税システムとは
口座振替により、国税・地方税を納税できます。
・ダイレクト納付・地方税共通納税システム利用の手続き
①ダイレクト納付
所轄税務署に「国税ダイレクト方式電子納税依頼書」を提出する必要があります。
②地方税共通納税システム
口座振替希望の金融機関に「口座振替依頼書」を提出する必要があります。
・ダイレクト納付のメリット
金融機関に出向くことなく、インターネット上で納税手続きができます。
毎月納付の源泉所得税や個人住民税の納税に利用すると、金融機関に出向く手間がなくなり、非常に便利です。
・ダイレクト納付のデメリット
インターネットで納税手続きを期限内に行わないといけないので、忘れないよう納税のスケジュール管理をきちんとする必要があります。
期限を過ぎて手続きを行うと、期限後納付となってしまいます。(延滞税がかかる場合もあります)
メリット・デメリットどちらも考えられますが、業務時間の短縮・作業効率のアップにもつながると思います。
質問等ございましたら、いつでもお気軽にご連絡よろしくお願いします。
※令和3年9月27日時点の法令に基づき、掲載しております。
- [2021.08.02]
- 交際費の領収書
個人事業でも法人でも、取引先等との交際費はいくらかある場合が多いと思います。
ひとくくりに交際費と言っても、贈答・ゴルフ・飲食など様々です。
ただどのような交際費でも、基本的には領収書は保存されているはずです。
この領収書には、年月日・金額・支払先の名称及び所在地はすでに記載されていることがほとんどだと思います。
しかし、その交際費の相手(取引先等)に関する情報は領収書を受け取った段階では記載されていません。
税務調査があった時、交際費はよく指摘を受けるものです。
「誰に対する贈答か?誰と一緒に行った飲食か?」
これが不明瞭であるがゆえに指摘を受け、過去の事なので自分でもよく覚えていない・・・というケースが多いです。
交際費の領収書には、相手の会社名や氏名を必ず書き込んでおきましょう。
もちろん領収書に書きこまず、交際費の報告書等を別で作成しておくことも考えられますが、ほとんどの場合は領収書に書き込むことで大丈夫だと思います。
よつば会計
中田 裕介
- [2021.06.29]
- 令和3年分の路線価図等
令和3年分の路線価図等は、7月1日(木)の11時に公開予定となっています。
よつば会計
中田 裕介
- [2021.04.11]
- 申告・納付期限
よつば会計、八反地です。
今年は気温が高い日が続いたこともあり、早々に桜が咲き葉桜の季節となりましたね。
今年も昨年に引き続き、新型コロナウイルスにより令和2年分確定申告の申告期限が延長され、それに伴い、振替納税の口座振替日も変更されています。
申告期限は令和3年4月15日(木)です。
口座振替を利用されていない方は、申告期限=納付期限となっておりますので注意が必要です。
口座振替日は、所得税:令和3年5月31日(月)/消費税:令和3年5月24日(月)
となっております。
残高不足により引落が出来なかった場合は、令和3年4月16日(金)から納付する日までの延滞税が必要となる場合がありますので、残高にはご注意ください。
- [2020.12.10]
- 住宅ローン控除のコロナ特例
利用している又は利用を検討している方も多い、「住宅ローン控除」。
おおまかに説明すると、個人が住宅ローン等を利用して、住宅の新築、取得又は増改築等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した一定の場合において、居住を開始した年から各年について税額控除を受けられるものです。
この中の一つのパターンとして、「中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行う」場合があります。
その場合ですと、「中古住宅を取得してから6か月以内に居住の用に供すること」という要件があります。
この要件について、「新型コロナの影響で、増改築等後の入居が遅れた場合、増改築等の契約の締結時期等の要件を満たせば、増改築等の完了の日から6か月以内の入居により要件を満たすことになる。」というコロナ特例が設けられています。
※ただし、入居期限は令和3年12月31日となっています。
☆中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行い、住宅ローン控除を検討されている方は要注意です!
よつば会計
中田裕介
- [2020.11.12]
- Go To トラベルキャンペーン
税理士の檜山です。
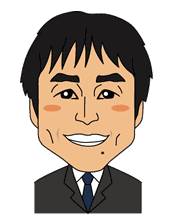
新型コロナウイルスの蔓延から半年以上が経過しました。
11月12日の感染者は1630名と過去最多となりました。本格的に第3波の襲来が訪れたと思っていいでしょう。
政府の方針としては、「GOTOキャンペーン」は経済をまわす観点からか中止は考えてないように思います。
「感染防止」と「経済循環」の両輪を維持しながら、生活していかなくてはいけません。
さて、10月末に観光庁のホームページにあるFAQが更新されていました。GOTOトラベルを利用し得した利益は一時所得の対象となります。
所得税法で規定する一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、 労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をさ します。一時所得の金額は、「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」 の計算式で算出し、所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して 総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
利益部分が50万円を超えなければ影響はありませんが、その年に住まい給付金や保険の満期、競馬で大当たりしたなどが重なり、合計した利益が年間50万円を超える場合には申告が必要となります。
↓の北木くんには、感染に気を付けて香川観光を楽しんでもらいたいです。そして「無事」と経済循環のため「香川の土産」を持って帰ってくれることを期待しています。
- [2020.10.16]
- 年末調整の申告書が大幅に変更されます
今年も年末調整の時期が近づいてきました。
令和2年の年末調整では、所得税の基礎控除の改正、所得金額調整控除の創設によって、申告書が大幅に変更されます。
①基礎控除申告書、②配偶者控除等申告書、③所得金額調整控除申告書の3つの申告書が「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という1枚の用紙になります。
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は、収入金額、配偶者や扶養家族の有無などにより、記入(提出)が必要かどうか判断する必要があります。
①基礎控除申告書
全員が記入(提出)します。
②配偶者控除等申告書
配偶者がいる人で、配偶者控除または配偶者特別控除を受ける人が記入(提出)します。
③所得金額調整控除申告書
給与等の収入金額が850万円超の人で下記の要件のいずれかに該当する人が記入(提出)します。
a. あなた自身が特別障害者
b. 同一生計配偶者が特別障害者
c. 扶養親族が特別障害者
d. 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生れ)
なお、例年通り「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」の提出も必要です。
大変複雑になっています。国税庁のホームページには、「年末調整がよくわかるページ」がありますので、参考にしてください。
〇年末調整がよくわかるページ
- 2025年4月(1)
- 2025年1月(1)
- 2024年12月(4)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(4)
- 2024年9月(3)
- 2024年8月(4)
- 2024年7月(3)
- 2024年6月(2)
- 2024年5月(3)
- 2024年4月(3)
- 2023年12月(4)
- 2023年11月(3)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(2)
- 2023年8月(4)
- 2023年7月(3)
- 2023年6月(3)
- 2023年5月(3)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(1)
- 2023年1月(1)
- 2022年12月(5)
- 2022年11月(3)
- 2022年10月(2)
- 2022年9月(2)
- 2022年8月(4)
- 2022年7月(5)
- 2022年6月(4)
- 2022年5月(3)
- 2022年4月(2)
- 2022年3月(1)
- 2022年1月(3)
- 2021年12月(4)
- 2021年11月(2)
- 2021年10月(4)
- 2021年9月(2)
- 2021年8月(5)
- 2021年7月(2)
- 2021年6月(4)
- 2021年5月(3)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(1)
- 2020年12月(4)
- 2020年11月(2)
- 2020年10月(1)
- 2020年9月(3)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(4)
- 2020年5月(4)
- 2020年4月(2)
- 2020年3月(1)
- 2020年2月(1)
- 2020年1月(3)
- 2019年12月(5)
- 2019年11月(2)
- 2019年10月(3)
- 2019年9月(5)
- 2019年8月(4)
- 2019年7月(3)
- 2019年6月(3)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(4)
- 2019年3月(1)
- 2019年2月(1)
- 2019年1月(1)
- 2018年12月(3)
- 2018年11月(2)
- 2018年10月(4)
- 2018年9月(2)
- 2018年8月(5)
- 2018年7月(4)
- 2018年6月(6)
- 2018年5月(2)
- 2018年4月(2)
- 2018年3月(1)
- 2018年2月(1)
- 2018年1月(4)
- 2017年12月(3)
- 2017年11月(2)
- 2017年10月(2)
- 2017年9月(3)
- 2017年8月(2)
- 2017年7月(2)
- 2017年6月(2)
- 2017年5月(2)
- 2017年4月(2)
- 2017年3月(2)
- 2017年2月(2)
- 2017年1月(2)
- 2016年12月(4)
- 2016年11月(2)
- 2016年10月(2)
- 2016年9月(2)
- 2016年8月(4)
- 2016年7月(2)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(1)
- 2016年3月(1)
- 2016年2月(1)
- 2016年1月(2)
- 2015年11月(3)
- 2015年10月(3)
- 2015年9月(3)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(2)
- 2015年6月(4)
- 2015年5月(2)
- 2015年4月(3)
- 2015年3月(2)
- 2015年2月(2)
- 2015年1月(4)
- 2014年12月(3)
- 2014年11月(1)
- 2014年10月(3)
- 2014年9月(2)
- 2014年8月(3)
- 2014年7月(1)
- 2014年6月(2)
- 2014年5月(1)
- 2014年4月(2)
- 2014年3月(3)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(1)
- 2013年12月(2)
- 2013年11月(3)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(7)
- 2013年7月(9)
- 2013年6月(6)
- 2013年5月(4)
- 2013年4月(5)
- 2013年3月(7)
- 2013年2月(2)
- 2013年1月(4)
- 2012年12月(4)
- 2012年11月(5)
- 2012年10月(8)
- 2012年9月(8)
- 2012年8月(4)
- 2012年7月(6)
- 2012年6月(2)
- 2012年5月(1)
- 2012年4月(1)
- 2012年3月(2)
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(1)
- 2011年12月(1)
- 2011年11月(1)
- 2011年10月(1)
- 2011年8月(2)
- 2011年1月(1)
- 2010年11月(1)