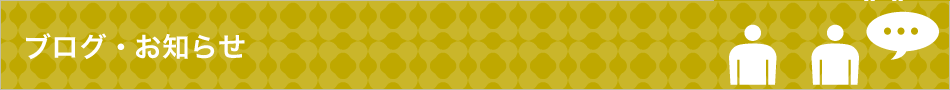- [2020.09.29]
- 新型コロナウィルス関連「固定資産税の減免」
新型コロナウィルスの影響で、「事業収入」が減少した「中小企業者等」が所有する「事業用家屋及び償却資産」の固定資産税等課税標準額を、「令和3年度分」に限り、ゼロまたは2分の1とする特例が講じられます。
※詳細は各市区町村へご確認ください。
【要件】
以下の2点の両方を満たす必要があります。
①中小企業者等に該当すること。
②令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。
【減免率】
・30%以上50%未満の減少であれば・・・2分の1
・50%以上の減少であれば・・・・・・・ゼロ
【注意点】
事業用であっても、土地は対象外です。もちろん、住宅用の家屋や土地も対象外です。
【適用する場合の手続き】
①まず必要な書類を用意したうえで、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。
②さらに必要な書類を用意したうえで、令和3年2月1日までに、各市区町村へ申告します。
【まとめ】
まずは、事業用家屋や事業用償却資産に固定資産税等がかかる予定なのか?の検討から。これが無しならそもそも関係ありません。
次に、事業収入の減少割合の計算です。ここで30%以上減少であれば、検討を進める必要があるかもしれません。
よつば会計
中田 裕介
- [2020.08.03]
- 共有の不動産にかかる固定資産税
土地や建物を所有していると課せられる固定資産税。
自分ひとりで所有していれば、毎年自分宛に通知が来て納付すれば済みます。
では、その土地や建物が、例えば親子でとか兄弟でなど、共有である場合はどうなるのでしょうか。
【原則、通知は代表者に送られてきます】
宛名は「〇〇様 外〇名様」として送られてきます。この場合、固定資産税の額は、全共有者分の総額です。
代表者は共有持分の多い人などで決められます。
固定資産税は連帯納税義務であり、共有者全員で全額の納税義務を負うことになります。ですので、共有割合ごとに別々に課税はできない、という考え方となります。
【代表者の変更は可能】
届出をすれば、通知が来る代表者を変更することができます。
【自治体によっては、共有持分ごとの通知・納付に変更することも可能】
広島市に確認したところ、分割納付の申請書を提出すれば、各人へ通知が来て各人の口座から振り替えられる形への変更はできるとのことです。
ただし、対応していない自治体もあるので注意です。
【まとめ】
原則的な形ですと、代表者に総額の通知が来て、代表者の口座から総額が振り替えられる、といったケースが多いと思います。
ただし、代表者は共有割合に応じて、他の共有者に請求する権利はあります。
後々のトラブルなどを考えると、共有割合ごとにきちんと負担額の精算をしておくべきだと考えます。
また、分割納付の申請ができるかどうか各自治体に確認し、できるようであれば申請しておくと、実際の共有持分に応じた通知と納付の形にできますし、毎年あとで精算するといった手間も省けるかもしれません。
よつば会計
中田 裕介
- [2020.07.14]
- 家賃支援給付金の受付がスタートしました。
家賃支援給付金が本日7/14からスタートしました。
対象は、5月からの売上高が一か月で前年同月比50%以上、または、連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少した事業者が支払った地代家賃の支払額です。
法人で最大600万円、個人事業主は最大300万円支給されます。
持続化給付金にくらべて、添付書類が増えていますので注意が必要です。
とくに賃貸借契約書に注意しないといけません。以下のような異動がある場合には、賃貸証明書が必要となります。これらの証明書には、申請者(賃借人)はもちろん、賃貸人の署名が必要ですので、事前に取り付けておかないといけません。
・契約書の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合
・契約書の賃借人と申請者の名義が異なる場合
・契約書の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合
・契約書が存在しない場合
また、添付する賃貸契約書には以下の箇所がわかるように印(マーカーなど)をつけないといけません。
- 賃貸借契約であることが確認できる箇所
- 土地・建物の契約であることが確認できる箇所
- 押印されている箇所(ただし、署名があれば押印不要)
- 賃貸人が現在の賃貸人と同じであることの確認
- 賃借人が申請者自身の名義であることの確認
- 対象となる土地・建物の住所がわかる箇所
- 2020年3月31日時点と申請日時点の両方で有効な契約であることの確認
- 申請する賃料、共益費・管理費
その他賃貸借契約以外でも注意が必要です。賃貸人が配偶者や両親であるケースや、賃貸人が申請法人の代表取締役であるケースはそもそも除外されています。
申請にあたっては、以下のサイトの申請要領をしっかりご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
※掲載の内容は、令和2年7月14日現在のものです。
- [2020.06.19]
- 新型コロナの影響と対応策 ~ 不動産賃貸業編 ~ ②
2.給付金
持続化給付金
残念ですが、個人経営の不動産賃貸業は「持続化給付金」の給付対象外となっており申請できません。
ただし、不動産賃貸業を法人で経営している場合は令和2年1月から令和2年12月の間の1か月間の売上高が前年の同期と比較し50%以上減少していれば申請することできます。
3.税の申告納税
新型コロナの影響で、納税資金に窮している場合には、税の申告納税期間の延長をすることができます。また、来年度に限り、事業用建物と事業用の償却資産に対して、固定資産税の50%減額や全額免除が受けられる措置が手当てされました。
① 申告期限の延長
新型コロナの影響で、申告書を提出することができない場合は、今年度は個人も法人も確定申告の期限は提出した日とされています。確定申告にかかる所得税・法人税などの納付期限も提出した日となりました。申告を遅くすることによって納税期限も遅くなります。
② 納税猶予
最近1か月間の売上高が前年の同期と比較し20%以上減少している場合、納期の到来している所得税・住民税・固定資産税の納税が1年間無利息で猶予されます。
これを受けるためには納税猶予の申請が必要です。
③ 固定資産税・都市計画税の減免
来年度の固定資産税のことですから、申請の手続きは令和3年1月31日までに行います。
令和2年2月から10月の間の連続する3か月の売上が前年の同期と比較し50%以上減少している場合は100%免除されます。
30%以上50%未満の場合には50%に減額されます。
対象となるのは事業用建物と事業用償却資産の固定資産税で、土地の固定資産税は減免されません。
※掲載の内容は、令和2年6月1日現在のものです。
- [2020.06.19]
- 新型コロナの影響と対応策 ~ 不動産賃貸業編 ~ ①
1.資金繰りの支援
新型コロナの影響で、家賃の滞納や免除・値下げなどが多発し借入金の返済に窮するような事態になった場合は、借入の条件や返済の条件が緩和された借入金を利用することができます。
返済の据置期間を設定することができ、10年くらいでゆっくり返し、無利息の期間もあります。
既存の借入金額が大きく、資金導入で間に合わない場合には、返済の据置期間を設定した借り換えや返済期間の延長などに対応してもらうことができます。
①日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
最近1カ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較し5%以上減少している場合に利用できます。
申し込みの相談窓口の混雑は大分解消されてきたようです。郵送で申し込むこともできます。
②セーフティネット保証4号(100%政府保証)
最近1か月間の売上高が前年の同期と比較し20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年の同期と比較して20%以上減少することが見込まれる場合に利用できます。
まずは取引している金融機関の担当者に相談してください。
③セーフティネット保証5号(80%政府保証)
市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です(不動産賃貸業は指定業種に含まれます)。
最近3か月間の売上高が前年の同期と比較して5%以上減少している場合に利用できます。
まずは取引している金融機関の担当者に相談してください。
※掲載の内容は、令和2年6月1日現在のものです。
- [2020.05.28]
- 役員報酬の減額
役員報酬は、原則事業年度を通じて毎月同額でなければなりません。
もし事業年度の途中で金額を変更した場合には、役員報酬の一部を損金に算入することができません。(経費になりません)
とはいえ新型コロナウイルスの影響により業績が急激に悪化し、役員報酬を減額せざるを得ない方も多いと思います。
このような非常事態でも役員報酬を減額することは認められないのでしょうか。
答えは、「新型コロナウイルスのような想定できなかった事情が起き、経営状況が著しく悪化した場合は、役員報酬を減額することが認めれらます。」(経費として認められます)
税務調査の際には、役員報酬減額に至った経緯を客観的かつ具体的に説明する必要がありますので、役員報酬の減額を決議した議事録を作成し、売上の激減が分かる試算表や資金繰り表などを保存しておくことが大切です。
また、一時的な資金繰りの都合や予算を達成できなかったなどの理由では役員報酬減額が認められない可能性がありますので、ご注意ください。
- [2020.05.04]
- 持続化給付金
税理士の檜山です。
4月30日の補正予算案が成立され、5月1日から持続化給付金の申請の受付が始まりました。2020年中の任意の月の売上高と前年同月の売上高を比較し50%以下となる場合、個人事業主には最大100万円、中小法人等には最大200万円を支給する制度です。
締め切りは2021年1月15日までです。
インターネットによる申請のみ行われており、確定申告書等の添付書類はPDF等により添付することとなります。電子申告により確定申告を行っている場合は、「メール詳細」(税務署からの収受印代わりになるもの)の添付も必要です。
2019年に新規開業した場合や法人成した場合には、一定の特例計算の方法も設けられています。
数件申請のサポートをさせて頂きましたが、システムも思ったより入力しやすいものでした。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
- [2020.04.02]
- 確定申告の期限延長
新型コロナウィルスの影響で、確定申告の期限が延長されました。
申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限及び納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されました。
振替納税を利用している場合の振替日も、申告所得税が令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税が令和2年5月19日(火)に延長されました。
申告はすでに終わったという方も多いと思いますが、振替日にも要注意です。
また、新型コロナウィルスの影響で国税を一時納付することができない方は、税務署へ申請することにより、原則1年以内に限り納税が猶予される場合もあります。
よつば会計
中田 裕介
- [2020.03.18]
- 令和2年から所得税制が変わります
令和2年の所得税から、給与所得控除・基礎控除の控除額の見直しが行われます。
① 給与所得控除の引き下げと上限の見直し
令和2年分の所得税から、サラリーマンなど給与所得者の給与収入から控除される「給与所得控除」の控除額が10万円引き下げられます。
また、控除額の上限額が適用される給与収入が850万円(改正前:1,000万円)に、控除額の上限が195万円(改正前:220万円)に引き下げられます。
② 基礎控除の引き上げと所得制限
個人の合計所得から一律に控除される「基礎控除」の控除額が10万円引き上げられます。(38万円 → 48万円)。
また、新たに所得制限が設けられ、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に縮小し、2,500万円を超えると控除の適用外になります。
③ 税負担に影響のない人
上記①と②の改正が同時に行われることで、年収850万円以下の人については、実質的な税負担は変わりません。扶養の範囲である103万円の壁なども変わりません。
④ 税負担に影響のある人
年収850万円超の人については、税負担が増えることになります。
ただし、障害者や扶養親族がいる人については、新たに「所得金額調整控除」が設けられ、税負担の緩和が図られます。
⑤ 個人事業主などは税負担が軽減されます
個人事業主など給与所得でない人のうち合計所得金額が2,400万円以下の人は、基礎控除の引き上げにより税負担が軽減されます。
- [2020.01.31]
- 単身児童扶養者とは?
令和1年分の年末調整と同時期に、職場へ「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方も多いと思います。
そしてその最下段に、「単身児童扶養者」という欄が新たに設けられています。
ここはどういった場合に記入するのでしょうか?
申告書の裏面に単身児童扶養者についての説明は書いてあります。そこでは・・・
「所得の見積額が48万円以下の児童について、児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする父または母のうち婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者」
と書いてあります。
ここで引っかかったのは、【婚姻をしていない者】の範囲でした。
一度婚姻をしてその後離婚をした人も、今は婚姻していないと言えそうだしなぁ・・・。
なかなかスッキリしなかったので、役所の窓口で確認してみました。
その結果・・・
「一度婚姻した後に離婚し現在一人で児童を扶養している場合は、単身児童扶養者には該当しない」とのことでした。
そもそもこの場合は以前よりある【寡婦】に該当します。
ここでいう【婚姻をしていない者】とは、「婚姻をせずに」児童と生計を一にしているような場合となるようです。
いわゆる「未婚の母・父」ということでしょうか。
日本語って難しい。
よつば会計
中田 裕介
- 2025年4月(1)
- 2025年1月(1)
- 2024年12月(4)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(4)
- 2024年9月(3)
- 2024年8月(4)
- 2024年7月(3)
- 2024年6月(2)
- 2024年5月(3)
- 2024年4月(3)
- 2023年12月(4)
- 2023年11月(3)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(2)
- 2023年8月(4)
- 2023年7月(3)
- 2023年6月(3)
- 2023年5月(3)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(1)
- 2023年1月(1)
- 2022年12月(5)
- 2022年11月(3)
- 2022年10月(2)
- 2022年9月(2)
- 2022年8月(4)
- 2022年7月(5)
- 2022年6月(4)
- 2022年5月(3)
- 2022年4月(2)
- 2022年3月(1)
- 2022年1月(3)
- 2021年12月(4)
- 2021年11月(2)
- 2021年10月(4)
- 2021年9月(2)
- 2021年8月(5)
- 2021年7月(2)
- 2021年6月(4)
- 2021年5月(3)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(1)
- 2020年12月(4)
- 2020年11月(2)
- 2020年10月(1)
- 2020年9月(3)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(4)
- 2020年5月(4)
- 2020年4月(2)
- 2020年3月(1)
- 2020年2月(1)
- 2020年1月(3)
- 2019年12月(5)
- 2019年11月(2)
- 2019年10月(3)
- 2019年9月(5)
- 2019年8月(4)
- 2019年7月(3)
- 2019年6月(3)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(4)
- 2019年3月(1)
- 2019年2月(1)
- 2019年1月(1)
- 2018年12月(3)
- 2018年11月(2)
- 2018年10月(4)
- 2018年9月(2)
- 2018年8月(5)
- 2018年7月(4)
- 2018年6月(6)
- 2018年5月(2)
- 2018年4月(2)
- 2018年3月(1)
- 2018年2月(1)
- 2018年1月(4)
- 2017年12月(3)
- 2017年11月(2)
- 2017年10月(2)
- 2017年9月(3)
- 2017年8月(2)
- 2017年7月(2)
- 2017年6月(2)
- 2017年5月(2)
- 2017年4月(2)
- 2017年3月(2)
- 2017年2月(2)
- 2017年1月(2)
- 2016年12月(4)
- 2016年11月(2)
- 2016年10月(2)
- 2016年9月(2)
- 2016年8月(4)
- 2016年7月(2)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(1)
- 2016年3月(1)
- 2016年2月(1)
- 2016年1月(2)
- 2015年11月(3)
- 2015年10月(3)
- 2015年9月(3)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(2)
- 2015年6月(4)
- 2015年5月(2)
- 2015年4月(3)
- 2015年3月(2)
- 2015年2月(2)
- 2015年1月(4)
- 2014年12月(3)
- 2014年11月(1)
- 2014年10月(3)
- 2014年9月(2)
- 2014年8月(3)
- 2014年7月(1)
- 2014年6月(2)
- 2014年5月(1)
- 2014年4月(2)
- 2014年3月(3)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(1)
- 2013年12月(2)
- 2013年11月(3)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(7)
- 2013年7月(9)
- 2013年6月(6)
- 2013年5月(4)
- 2013年4月(5)
- 2013年3月(7)
- 2013年2月(2)
- 2013年1月(4)
- 2012年12月(4)
- 2012年11月(5)
- 2012年10月(8)
- 2012年9月(8)
- 2012年8月(4)
- 2012年7月(6)
- 2012年6月(2)
- 2012年5月(1)
- 2012年4月(1)
- 2012年3月(2)
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(1)
- 2011年12月(1)
- 2011年11月(1)
- 2011年10月(1)
- 2011年8月(2)
- 2011年1月(1)
- 2010年11月(1)