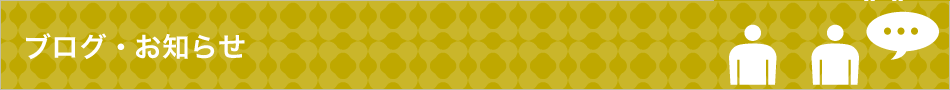- [2018.12.06]
- 今年の年末調整の注意点
気が付けば、あっという間に12月。年々1年が早く感じるのは、年のせいでしょうか?
今年は、配偶者控除等の改正に伴い、以下の点に注意が必要です。
①「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚に分かれました。
②配偶者控除の適用を受けるには、「配偶者控除等申告書」の提出が必要になります。
③新しくなった「配偶者控除等申告書」には、給与所得者本人とその配偶者の所得の見積額と、所得の区分判定を記載します。
配偶者控除等申告書の記載例については以下の国税庁のサイトで調べることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm
また、以下の国税庁のサイトでは、金額を入力すると自動で判定・計算してくれる「配偶者控除等申告書」の入力用ファイルが準備されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku.htm
※掲載の情報につきましては、2018年12月6日現在のものです。
- [2018.11.30]
- 平成30年1月からの配偶者控除等の改正の影響は?②
年収の壁は他にもある
最高38万円の控除を適用できる妻の収入の上限が年150万円に引き上げられましたが、単純に年収150万円まで働けば、世帯手取り額が増えるとは限りません。
配偶者(特別)控除以外にも、「年収の壁」はあります。例えば、社会保険には「130万円(又は106万円)の壁」があり、妻自身が社会保険料を負担することになると、妻の給与年収が増加しても一定額までは世帯の手取額が減少する逆転現象が生じます。
◆金額別に見た「年収の壁」
・100万円の壁 ・・・ 住民税の壁(各自治体によって違いがあります)
・103万円の壁 ・・・ 所得税の壁
・106万円の壁 ・・・ 大企業の社会保険の壁
・130万円の壁 ・・・ 社会保険の壁
・150万円の壁 ・・・ 拡大した配偶者特別控除の壁
※掲載の情報につきましては、2018年11月30日現在のものです。
- [2018.11.30]
- 平成30年1月からの配偶者控除等の改正の影響は?①
配偶者控除に所得制限が設けられる
妻のパート収入が年103万円以下であれば、夫は最高38万円の「配偶者控除」を受けることができますが、改正によって夫に所得制限が設けられました。
夫の収入(給与の収入)が年1,120万円を超えると控除額が逓減(38万円→26万円→13万円)し、年1,220万円を超えると適用が受けられなくなります。
夫の収入が高い場合には、増税になりますが、夫の年収が1,120万円以下で妻の年収が103万円以下の範囲であれば、改正前と変わりありません。
配偶者特別控除の控除枠が拡大
妻の年収が年103万円を超えると、妻の収入に所得税がかかります。これは、改正後も変わりません。また、夫は配偶者控除の適用ができなくなりますが、代わって「配偶者特別控除」を受けることができます。
配偶者特別控除は、妻の年収によって段階的に縮小されますが、改正によって、夫の所得から最高38万円の控除を適用できる妻の収入は年150万円以下まで拡大されています。(改正前は年105万円未満)。
配偶者特別控除にも配偶者控除と同様の所得制限が設けられましたが、控除対象となる妻の年収が年201万円までは拡大されたため、減税になるケースが増えます。
※掲載の情報につきましては、2018年11月30日現在のものです。
- [2018.10.25]
- 修繕費か?資本的支出か?Part2
固定資産の修理や改良をした場合、一度で経費となる修繕費となるか、数年に分けて経費となる資本的支出となるかの判断には、いつも悩まされます。
今回は、不動産賃貸業を例に考えていきます。
不動産賃貸業を営むAさんは、貸アパートの水廻りが傷んできたので、システムキッチン(70万円)とユニットバス(50万円)を新しくしました。
この場合、システムキッチンとユニットバスを新しくした工事代金120万円は、修繕費になるのでしょうか?それとも資本的支出になるのでしょうか?
答えは、資本的支出となります。
理由は、どちらも物理的に建物に取り付けられた新たな設備であるからです。
資本的支出になる場合、工事代金120万円は一度に経費にすることはできず、取り付けた建物の耐用年数で減価償却し、経費となります。
アパートが鉄筋コンクリート造なら、耐用年数である47年間で償却します。
※掲載の情報につきましては、2018年10月25日現在のものです。
- [2018.09.28]
- 修繕費か?資本的支出か?
機械や建物の修理等に支出した費用は、それが固定資産の取得にあたるかどうか、修繕費として経費(損金)処理できるか、資本的支出として資産計上すべきかの判断が必要になります。
例えば、車両へ機器取付とタイヤ交換を同時に行った場合はどのように判断したらよいのでしょうか?
①常時搭載する機器の取付け
既存車両に常時搭載するカーナビやドライブレコーダー、ETCシステムなどを新たに取り付けるために購入した場合、これらの機器は単独の資産の取得にはなりません。
この場合は、車両に新たな機能を追加することになり、その車両への資本的支出として資産計上が必要になります。ただし、費用の合計額が20万円未満であれば、修繕費とすることができます。
②車両全てのタイヤ交換
同時に行ったタイヤ交換の修理等は、レギュラーからスタッドレスへの交換などタイヤそのものの機能を向上させるものでない限り、維持管理・原状回復に係る修理等として修繕費で処理することになります。
③機器取付けとタイヤ交換の費用を区分
整備会社から交付された見積書や請求書に従って、カーナビ等の「機器取付け」の費用(資本的支出)と「タイヤ交換」の費用(修繕費)を区分する必要があります。
※掲載の情報につきましては、2018年9月30日現在のものです。
- [2018.09.11]
- 所得拡大促進税制の改正
所得拡大促進税制が改正されました。
青色申告である中小企業者等が対象となり、平成30年4月1日以降に開始される事業年度から適用となります。
※青色申告の個人事業主でも大丈夫で、個人事業主の場合は平成31年分から適用となります。
(注)この記事においては簡単にまとめますので、適用を検討される場合は、中小企業庁のHPに公表されているガイドブック等を必ず参考にしてください。
この税制は、簡単に言うと「従業員への給料を増やしたら法人税や所得税を一部控除してあげますよ」というものです。
「所得拡大促進税制」となっていますが、会社や事業主の所得の拡大ではなく、そこで働く従業員さんの所得の拡大を促進する目的となっています。
では実際に適用するための要件ですが、以下の2つを満たす必要があります。
①「給与等支給額」が前年度より増加していること
②「継続雇用者給与等支給額」が前年度比で1.5%以上増加していること
ここで気をつけなければいけないのが、「給与等支給額」と「継続雇用者給与等支給額」は別物という点です。
「給与等支給額」は、「役員等を除く全ての国内従業員に支払った給与等の総額」となっています。ですので、パート・アルバイト・日雇い労働者も計算に含めます。ただし、役員等は除かれていますので、役員やその家族の給料のみを引き上げてこの税制の恩恵を受ける、ということはできません。
次に「継続雇用者給与等支給額」は、「継続雇用者に支払った給与等の総額」となっていますが、この「継続雇用者」とは、以下の全てを満たす者となります。
①前事業年度及び適用年度の全ての月で、給与等の支給を受けた国内雇用者
②前事業年度及び適用年度の全ての期間において、雇用保険の一般被保険者
③前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において、高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない
上で分かるとおり、「継続雇用者給与等支給額」の方が、対象者の要件が多いため集計に手間がかかりそうです。
決算よりも前に、早めの検討が必要です。
※この税制には上乗せ措置がありますが、また次の機会に書かせて頂きます。
中田裕介
- [2018.08.10]
- 大雨災害で被災されご自宅等に損害を被った方へ
豪雨、酷暑、台風など今までにない異常気象によりとても多くの方々が被害に遭われました。
被災された皆様並びにご家族の皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。
災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合、雑損控除の適用を受けることができます。この雑損控除とは別に、その年の所得金額が1000万円以下の方が災害にあった場合、災害減免法による所得税の軽減免除制度が設けられています。
どちらを適用する場合でも確定申告を提出しなければならず、市区町村から交付を受ける罹災証明書等の添付が必要です。罹災証明の取得には時間がかかるため、早めの手配が望まれます。
|
|
雑損控除(所得控除) |
災害減免法(税額免除・軽減) |
|
損失原因 |
災害、盗難、横領 |
災害 |
|
対象資産 |
自宅や家財など生活に通常必要な資産 |
住宅や家財(但し、損害額が資産の価額の1/2以上である場合) |
|
控除金額または所得税の軽減額 |
※いずれか多い金額 |
所得金額が 500万円以下・・・全額免除 500~750万円・・・1/2軽減 750~1,000万円・・・1/4軽減 |
|
所得制限 |
なし |
損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下 |
|
繰越制度 |
原則3年(大震災は5年) |
減免を受けた年の翌年以降は適用不可 |
どちらが有利かは収入金額や損害の規模によって変わりますので、適用される場合には最寄りの税務署または税理士へご相談ください。
よつば会計 檜山
- [2018.07.17]
- ものごとの見方
税理士の手嶋です。
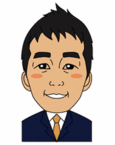
最近、弁護士の先生と不動産に関する案件に取り組んでいます。
意見を交換していて感じることが、ひとつの事案についてかなり見方や想定している場面が違うことです。
税理士はトラブルが発生していない状況の延長で物事を考えていますが、
弁護士は最悪の状況を想定して物事を考えています。
考え方について質問をすると「修羅場ばかりを見ていますから」とのこと。
なるほど、平穏の中で仕事をする税理士の知らない世界です。
知らない世界のことだから考えが及びません。
税理士としての知識や経験の延長では辿り着かないものの見方は非常に参考になります。
セカンドオピニオンでも無理ですね、税理士の実務の範囲を超えていますから。
他の業種の方と仕事をする楽しみってこういうところですね。
同じように気づきを与えられる存在でありたいです。
- [2018.07.10]
- 有給休暇 ~ 計画的付与制度について~
現在議論されている「働き方改革」では、「有休が10日以上付与されている従業員を対象に、そのうち5日分については会社が社員に与えることを義務付ける」ことが検討されています。
しかし、現状をみると、従業員の有休取得が進んでいる会社はそんなに多くはないのではないでしょうか?
有休の取得を促進するために「計画的付与制度」について説明します。
◆計画的付与制度とは
有休のうち、5日を超える分については、あらかじめ有休の取得日を割り振るものです。
計画的付与制度には、以下の3つのパターンが考えられます。
①一斉付与方式
全従業員に一斉に有休を与える。
②交代制付与方式
班やグループ別に交替で有休を与える。
③個人別付与方式
個人別に、夏季、年末年始、ゴールデンウィークのほか、誕生日や結婚記念日など従業員の個人的な記念日をあらかじめ指定して有休を与える。
計画的付与制度の導入に当たっては、就業規則への規定と労使協定の締結が必要になります。なお、労使協定は、労働基準監督署へ届け出る必要はありません。
有休の取得が増えると、業務量が減って、生産性が低下し、売上が下がるのではないか、という心配もあるかと思います。
しかし、業務改善を進めて、有休取得率を大幅に増加させたことにより、離職率が下がり、業績がアップした事例もあります。
残業削減を含めて、業務の効率化を図り、従業員のモチベーションを上げながら、業績向上を図る取り組みが必要となっているのではないでしょうか。
- [2018.07.10]
- 有給休暇 ~ 素朴な疑問 ~
◆有休休暇の付与日数
有休は、従業員が雇い入れの日から6か月以上継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上あれば、最低10日の日数を与えなければならないとされています。以後は1年ごとに有休付与日数が増えていきます。
【勤続年数】 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月
【付与日数 】 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
◆従業員から有給の取得申請があれば、繁忙期や人手が足りないときでも有給休暇を与えなければならないのでしょうか?
有休は、原則として、従業員から請求のあった時季に与えなければなりません。
「同じ時季に多くの従業員が休む」とか「代替要員の配置が難しい」など、事業の正常な運営が妨げられる場合は、時期の変更を求めることができます。
ただし、単に「日常的に忙しい」とか「人手が足りない」などの理由では、時季の変更を求めることはできません。慢性的な人手不足の会社では、従業員が有休を取れなくなってしまうからです。
◆業務や他の従業員との調整が必要なため、有給申請は事前にすることを義務付けていますが、それでよいでしょうか?
有給取得の事前申請の期間が合理的であれば問題ありません。
「合理的な期間」のとらえ方は、会社の規模や業種によって異なりますが、少人数の会社ほど、従業員一人当たりの負担・責任も大きいことから、事前申請の期間は比較的長くなることも想定されます。
◆未消化の有休を従業員から買い取ってもよいのでしょうか?
原則として、未消化分の有休を買い取ることは認められていません。
有給休暇とは、従業員が休日以外の日に、有給で休暇を取得することを労働基準法が定めた制度だからです。
◆有休を取得した従業員には、皆勤手当を支払わなくてもよいのでしょうか?
有給休暇以外の出勤日に出勤しているならば、原則として皆勤手当は支給しなければなりません。
皆勤手当や賞与の算定等に際して、有給取得日を欠勤や欠勤に準じた取り扱いにすることは、従業員への不利益な取扱いになります。
- 2025年4月(1)
- 2025年1月(1)
- 2024年12月(4)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(4)
- 2024年9月(3)
- 2024年8月(4)
- 2024年7月(3)
- 2024年6月(2)
- 2024年5月(3)
- 2024年4月(3)
- 2023年12月(4)
- 2023年11月(3)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(2)
- 2023年8月(4)
- 2023年7月(3)
- 2023年6月(3)
- 2023年5月(3)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(1)
- 2023年1月(1)
- 2022年12月(5)
- 2022年11月(3)
- 2022年10月(2)
- 2022年9月(2)
- 2022年8月(4)
- 2022年7月(5)
- 2022年6月(4)
- 2022年5月(3)
- 2022年4月(2)
- 2022年3月(1)
- 2022年1月(3)
- 2021年12月(4)
- 2021年11月(2)
- 2021年10月(4)
- 2021年9月(2)
- 2021年8月(5)
- 2021年7月(2)
- 2021年6月(4)
- 2021年5月(3)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(1)
- 2020年12月(4)
- 2020年11月(2)
- 2020年10月(1)
- 2020年9月(3)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(4)
- 2020年5月(4)
- 2020年4月(2)
- 2020年3月(1)
- 2020年2月(1)
- 2020年1月(3)
- 2019年12月(5)
- 2019年11月(2)
- 2019年10月(3)
- 2019年9月(5)
- 2019年8月(4)
- 2019年7月(3)
- 2019年6月(3)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(4)
- 2019年3月(1)
- 2019年2月(1)
- 2019年1月(1)
- 2018年12月(3)
- 2018年11月(2)
- 2018年10月(4)
- 2018年9月(2)
- 2018年8月(5)
- 2018年7月(4)
- 2018年6月(6)
- 2018年5月(2)
- 2018年4月(2)
- 2018年3月(1)
- 2018年2月(1)
- 2018年1月(4)
- 2017年12月(3)
- 2017年11月(2)
- 2017年10月(2)
- 2017年9月(3)
- 2017年8月(2)
- 2017年7月(2)
- 2017年6月(2)
- 2017年5月(2)
- 2017年4月(2)
- 2017年3月(2)
- 2017年2月(2)
- 2017年1月(2)
- 2016年12月(4)
- 2016年11月(2)
- 2016年10月(2)
- 2016年9月(2)
- 2016年8月(4)
- 2016年7月(2)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(1)
- 2016年3月(1)
- 2016年2月(1)
- 2016年1月(2)
- 2015年11月(3)
- 2015年10月(3)
- 2015年9月(3)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(2)
- 2015年6月(4)
- 2015年5月(2)
- 2015年4月(3)
- 2015年3月(2)
- 2015年2月(2)
- 2015年1月(4)
- 2014年12月(3)
- 2014年11月(1)
- 2014年10月(3)
- 2014年9月(2)
- 2014年8月(3)
- 2014年7月(1)
- 2014年6月(2)
- 2014年5月(1)
- 2014年4月(2)
- 2014年3月(3)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(1)
- 2013年12月(2)
- 2013年11月(3)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(7)
- 2013年7月(9)
- 2013年6月(6)
- 2013年5月(4)
- 2013年4月(5)
- 2013年3月(7)
- 2013年2月(2)
- 2013年1月(4)
- 2012年12月(4)
- 2012年11月(5)
- 2012年10月(8)
- 2012年9月(8)
- 2012年8月(4)
- 2012年7月(6)
- 2012年6月(2)
- 2012年5月(1)
- 2012年4月(1)
- 2012年3月(2)
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(1)
- 2011年12月(1)
- 2011年11月(1)
- 2011年10月(1)
- 2011年8月(2)
- 2011年1月(1)
- 2010年11月(1)