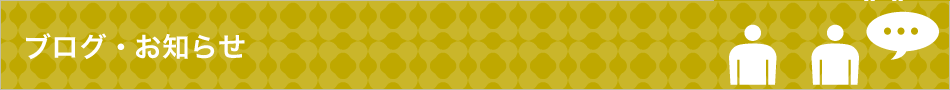- [2013.07.13]
- 払い過ぎた利息が戻ってきたら税金はかかるの?
税理士の手嶋です。

過払い金請求ってわかりますか?
消費者金融等からお金を借りて、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超える金利の
支払いをしていた場合に、その払い過ぎた利息のことを過払い金といいます。
平成13年5月までの法定上限金利は40.004%でした。
1,000万円借りたら、金利が400万円です。すごい金額です。
これを利息制限法で計算すると金利は150万円となり、払い過ぎ部分は250万円です。
この上限金利40.004%はその後、出資法の上限金利である29.2%になり、
そして利息制限法の20.0%に変わっています。
数年前までこの過払い金請求が弁護士、司法書士に特需をもたらしていましたが、
それも今はだいぶ落ち着いてきたようです。
この過払い金請求をし、返還があった場合の税務上の取り扱いについては以下のようになります。
① 家事上の借入金の場合
過払い金・・・課税関係なし
過払い金に付された利息(以下「利息」)・・・支払いを受けた日の年分の雑所得
② 事業にかかる借入金の場合
(1)事業的規模の不動産所得・事業所得等の必要経費に算入していた場合
過払い金・・・判決のあった日の即する年分の総収入金額に算入
利息 ・・・支払いを受けた日の年分の総収入金額に算入
(2)事業的規模でない不動産所得・事業所得等の必要経費に算入していた場合
過払い金・・・必要経費に算入した各年分の所得税を修正
利息 ・・・支払いを受けた日の年分の総収入金額に算入
過払い金に付された利息については所得が生じたと考えて家事上、業務上を問わず
課税対象になっています。
家事上の雑所得の場合、給与所得者なら20万円を超える金額だと申告義務が生じますが、
20万円以下の金額なら申告義務はありません。
事業にかかる借入金で事業的規模の場合、遡る必要がなく、その年の確定申告に
反映させればよいので簡単です。
事業的規模でない場合、過去の申告につき修正申告をする必要があるため少々面倒です。
ただし、国税の時効は法定納期限から5年なので過払い金問題の時期から考えると
申告の必要はないものがほとんどかもしれませんね。
- [2013.06.25]
- 税務署の事務年度
税理士の手嶋です。

先週はよく雨が降りましたね。
それまで梅雨らしくなかった分、まとめてでした。
土曜日に野球観戦したのですが、その日だけ晴れでした。
誰かの行いが良かったのでしょう。
試合は残念ながらカープの完封負けでしたが・・・。
さて、こんな梅雨時期に年度末を迎える人たちがいます。
税務署の人たちです。
税務署は7月から6月までが事務年度となっており、
毎年7月10日が定期異動日です。
税務職員は7月に異動して調査法人を選定し、調査にかかります。
そのため8月~12月までの税務調査は十分に時間があるため要注意ですね。
本格的な調査はやはり秋が多いです。
1月~3月については個人の確定申告の時期になります。
税務署、税理士とも多忙なため税務調査は少ないです。
5月~6月については6月が事務年度の区切りになるため、
調査を長引かせられない事情があります。
ただし繰越しとか引き継ぎという手もあるようです。
また税務職員には件数のノルマがあります。
予定通りに進んでいなければ、件数消化もこの時期になります。
件数のノルマのことは元国税の方が話していました。
あと増差の発見はヒット、重加算対象の発見はホームランとも。
税務職員にもいろいろと事情があるのですね。
- [2013.06.13]
- 事業年度って適当に決めていいの?
税理士の手嶋です。

本日のお題は会社の事業年度についてです。
事業年度は原則として会社の任意で定めることができます。
そして事業年度は1年を超えても問題ありませんが、法人税や消費税は1年を超える事業年度を
認めていないため通常は1年を単位に事業年度を設定しています。
平たく言うと、1年に1回は税金を計算して納税して下さいってことです。
1年を超える事業年度を設定できる必要があるのかという疑問は置いといて、
では何の制約もない場合にどうやって事業年度を決めるべきなのでしょう。
商売には少なからず季節変動というものがあります。
例えば3月の年度末に大きな利益が計上される場合には、この時期が上半期にくるように
事業年度を設定するのが良いのです。
なぜなら上半期にすることで、利益が予想以上に多かった場合には節税について
考えることができ、逆に利益が予想より少なかった場合には下半期の営業について
戦略を練り直すといった手を打つことができるからです。
これが3月決算の会社の場合には、利益が多いときはそれに対処できるわけもなく
その分納税が増え、利益が少ないときはそのまま赤字決算になることも考えられます。
3月が終わってからの出たとこ勝負になるため、これでは予定が立ちません。
事業年度の変更は株主総会を開催して定款を変更すれば簡単にできます。
上記のような場合には変更を考えてみてはいかがでしょうか。
ただし税理士は2月と3月は個人の確定申告で忙しいから、
できるだけ12月決算と1月決算はやめてほしいと思っています・・・。
- [2013.04.10]
- 金融円滑化法終了
税理士の手嶋です。

金融円滑化法終了に伴う今後の影響とサービサーを利用した事業再生セミナーに参加してきました。
講師は弁護士の杉浦正敏氏で、債務者の再生支援を行う一方で、債権者から債権を買い取る債権回収株式会社(サービサー)の取締役をされているという方でした。
平成21年から始まった金融円滑化法ですが、全国約420万社のうち推計で30万~40万社が利用していると言われています。
そしてここ数年の景気悪化にもかかわらず、同制度の利用により倒産件数は減少していることから倒産予備軍が増加していると分析されていました。
サービサーについては、日本における成り立ち、設立に関する規制、反社会的勢力の排除の仕組み、法務大臣・警察庁長官による業務の監督などに加え、実際のサービサーの債権買付けについての話もあり興味深い内容でした。
他にもサービサーを利用した事業再生パターンの事例を紹介していましたが、特殊な技術を持っているといった企業自体の強みがあることが前提のため、普通の中小企業にはハードルが高いように思いました。
この問題に特効薬はないので、企業は経営改善を重ねて事業を黒字化し、資金繰りを正常化していくほか道はないですね。
アベノミクスで実体経済も回復していけば追い風になり良いのですが、一体どうなるのでしょうか。
- [2013.01.13]
- お守りと消費税
税理士の檜山です。
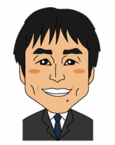
平成25年もはじまって2週間ばかり過ぎました。年末年始に食べ過ぎたのもあって、今年はランニング生活のスタートは遅めです。
今年も元気に一年を過ごせるように、3日に近くの神社へ初詣に行ってきました。毎年同様、昨年お世話になったお守りを奉納し、お参りをしておみくじをひいてお守りを買って帰りました。
お守りといえば、以前月次監査でお邪魔したクライアントの経理の方からこんな質問を受けました。
「会社が神社でお守りやお札を購入した場合、消費税はかかっているんですよね?」
結論から言うと消費税は課税されません。
そもそも消費税が課税される取引は、以下の4つの要件を満たすものとされています。
- 国内で行われること
- 事業者が事業として行うこと
- 対価を得て行われること
- 資産の譲渡、資産の貸付け、役務提供のいずれかであること
上の要件を一読すると、消費税が課税される取引に見えます。しかし、法人税法の基本通達において「宗教法人のお守り等の販売は、売価と仕入原価の関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする」と規定しており、事業性および対価性の観点から課税要件を満たさないと解されます。
おみくじについても同様な考えです。今年の私のおみくじは末吉でした。旅行の項目は良かったので、今年はもう少し県外のマラソン大会に行きたいものです。
- [2012.10.16]
- 広島菓子博2013の協賛金
税理士兼自称市民ランナー檜山です。
つい先日東京マラソンの抽選が行われたようです。東京マラソンが行われる2月末は所得税の確定申告の繁忙期と重なる為、まだ申し込んだことはありません。知り合いからは、「受からんから、申し込むだけ申し込みなさい」と言われているので来年あたりは申し込んでみようかなとも思っています。
来年4月は、全国のお菓子が一堂に広島に集結する博覧会「ひろしま菓子博2013」が開催されます。開催頻度はほぼ4年に1度しか行われませんが、今回でなんと26回目を迎えます。明治44年から始まっている歴史の深い博覧会です。
開催期間は、25年4月19日(金)~5月12日(日)の24日間。場所は広島市民球場跡地を中心にその周辺を使ったかなり大規模なものとなります。
この博覧会に対する協賛者が支出する費用の税務上の取り扱いについて、国税庁のホームページで公開されています。(URL)
基本的には、協賛についての支出は「広告宣伝費」として経費処理することで問題ない様です。注意すべきは、経費として処理する金額は広告宣伝期間で按分計算することです。一番多いと思われるホームページのバナー広告については”協賛承諾日の翌月から会期末まで”となっていますので、8月に承諾があったなら9月から翌年5月までの期間で経費按分が必要となります。
甘いもの好きとしては、とても楽しみな博覧会です。前売り券も購入したので後はわくわくしながら開催日を待つだけです。
- [2012.06.13]
- 梅雨になった・・・・・
広島も梅雨に入り、はっきりしない天気が続くのかと思うと、憂鬱になりそうです。ニュースでは「自分勝手な思いで人を殺害する事件」が報道され、更に憂鬱にさせられます。
ふと考えるのですが、人と人の関り方が気になっています。
当事務所では、税務署への提出をほとんど電子申告でやっています。最近は通信手段が発達して、電子通信で業務のほとんどを完了できるようになってきました。
とてもスピーディに効率良く仕事が進むことは、素晴らしいことです。更に人との繋がりを忘れずに、より大切にしていきたいとおもいました。 藤川
- [2011.10.18]
- 「経営セーフティ共済」が新しくなりました。
平成23年10月1日から、「経営セーフティ共済」が変わりました。
掛金月額の上限が、8万円から20万円に引き上げられ、掛金の積立限度額が、320万円から800万円に引き上げられました。
すでに加入されている企業にとっても、まだ加入されていない企業にとっても、活用する幅が広がります。
掛金の増額や、共済への加入を検討すべき企業も多いかもしれません。
- 2025年4月(1)
- 2025年1月(1)
- 2024年12月(4)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(4)
- 2024年9月(3)
- 2024年8月(4)
- 2024年7月(3)
- 2024年6月(2)
- 2024年5月(3)
- 2024年4月(3)
- 2023年12月(4)
- 2023年11月(3)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(2)
- 2023年8月(4)
- 2023年7月(3)
- 2023年6月(3)
- 2023年5月(3)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(1)
- 2023年1月(1)
- 2022年12月(5)
- 2022年11月(3)
- 2022年10月(2)
- 2022年9月(2)
- 2022年8月(4)
- 2022年7月(5)
- 2022年6月(4)
- 2022年5月(3)
- 2022年4月(2)
- 2022年3月(1)
- 2022年1月(3)
- 2021年12月(4)
- 2021年11月(2)
- 2021年10月(4)
- 2021年9月(2)
- 2021年8月(5)
- 2021年7月(2)
- 2021年6月(4)
- 2021年5月(3)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(1)
- 2020年12月(4)
- 2020年11月(2)
- 2020年10月(1)
- 2020年9月(3)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(4)
- 2020年5月(4)
- 2020年4月(2)
- 2020年3月(1)
- 2020年2月(1)
- 2020年1月(3)
- 2019年12月(5)
- 2019年11月(2)
- 2019年10月(3)
- 2019年9月(5)
- 2019年8月(4)
- 2019年7月(3)
- 2019年6月(3)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(4)
- 2019年3月(1)
- 2019年2月(1)
- 2019年1月(1)
- 2018年12月(3)
- 2018年11月(2)
- 2018年10月(4)
- 2018年9月(2)
- 2018年8月(5)
- 2018年7月(4)
- 2018年6月(6)
- 2018年5月(2)
- 2018年4月(2)
- 2018年3月(1)
- 2018年2月(1)
- 2018年1月(4)
- 2017年12月(3)
- 2017年11月(2)
- 2017年10月(2)
- 2017年9月(3)
- 2017年8月(2)
- 2017年7月(2)
- 2017年6月(2)
- 2017年5月(2)
- 2017年4月(2)
- 2017年3月(2)
- 2017年2月(2)
- 2017年1月(2)
- 2016年12月(4)
- 2016年11月(2)
- 2016年10月(2)
- 2016年9月(2)
- 2016年8月(4)
- 2016年7月(2)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(1)
- 2016年3月(1)
- 2016年2月(1)
- 2016年1月(2)
- 2015年11月(3)
- 2015年10月(3)
- 2015年9月(3)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(2)
- 2015年6月(4)
- 2015年5月(2)
- 2015年4月(3)
- 2015年3月(2)
- 2015年2月(2)
- 2015年1月(4)
- 2014年12月(3)
- 2014年11月(1)
- 2014年10月(3)
- 2014年9月(2)
- 2014年8月(3)
- 2014年7月(1)
- 2014年6月(2)
- 2014年5月(1)
- 2014年4月(2)
- 2014年3月(3)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(1)
- 2013年12月(2)
- 2013年11月(3)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(7)
- 2013年7月(9)
- 2013年6月(6)
- 2013年5月(4)
- 2013年4月(5)
- 2013年3月(7)
- 2013年2月(2)
- 2013年1月(4)
- 2012年12月(4)
- 2012年11月(5)
- 2012年10月(8)
- 2012年9月(8)
- 2012年8月(4)
- 2012年7月(6)
- 2012年6月(2)
- 2012年5月(1)
- 2012年4月(1)
- 2012年3月(2)
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(1)
- 2011年12月(1)
- 2011年11月(1)
- 2011年10月(1)
- 2011年8月(2)
- 2011年1月(1)
- 2010年11月(1)