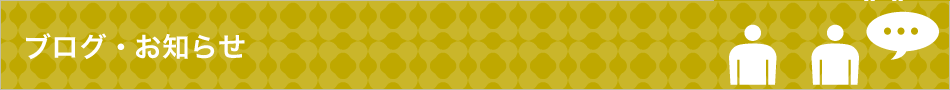- [2024.07.05]
- 税務手続きのデジタル化への対応
社会のデジタル化の進展に伴い、税・社会保障分野のデジタル化も急速に進んでいます。
現在、国税庁が行っている取り組みについて、代表的なものを2つ紹介します。
【キャッシュレスで「行かない」納付】
国税の納付については、金融機関やコンビニなどで現金で支払う方も多いのではないでしょうか。
次のようなキャッシュレス納付を利用すれば、窓口に行かずに国税を納付することができ、現金管理の事務負担も減らすことができます。
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・インターネットバンキング
・クレジットカード納付など
なお、e-Taxで申告を行った法人等には、令和6年5月以降「納付書」が送付されなくなりました。
【確定申告等の控えへの収受印の廃止】
令和7年1月から、確定申告書等の控えへの収受印の押印が廃止されます。
提出事実・提出年月日を確認する方法としては、電子申告(e-Tax)で確定申告書等を提出している場合は、e-Taxの「受信通知」や「電子申請等証明書」によることになります。
現在電子申告をしている方は、上記の「受信通知」により提出したことを証明することができますが、紙で提出している方は、収受印がなくなりますので、今までのように申告書の控えをコピーして提出、では証明することができなくなります。
キャッシュレス納付や電子申告(e-Tax)の利用を検討してみるよい機会かもしれませんね。
- [2024.07.05]
- 38年前と違う
小学校
①胸につけている名札は登下校中は裏にしておく
②給食は残してもよく、昼休憩に残って食べなくてもよい
③長ズボンを履いてもよい
④学校からの連絡がアプリでくる
⑤夏休みに学校のプールに毎日行けない
⑥昔は違ったと言うと嫌われる
よつば会計
中田裕介
- [2024.06.19]
- 相続土地国庫帰属制度の運用状況
税理士の檜山です。
昨年4月からスタートした相続土地国庫帰属制度。
相続はしたものの土地の管理ができない・遠くにあるため利用する予定がないなど、土地を手放したいというニーズに応えるために創設された制度です。
目的へのアプローチはいいのですが、国庫帰属までのハードルが高く私の周りで申請したという話はあまり聞いていません。
制度開始から1年を経過したこともあり、法務省から現時点の統計データが公表されました。
(以下、令和6年5月31日現在の数値です)
申請件数 2207件
地目別
田・畑 837件(38%)
宅地 793件(36%)
山林 338件(15%)
その他 239件(11%)
帰属件数 460件(20.8%)
地目別
田・畑 137件(16.3%)
宅地 190件(24.0%)
山林 16件( 4.7%)
その他 117件(49.0%)
審査中の数が結構あるのかもしれませんが、帰属件数は20%(5件に1件)の割合です。
地目ごとに見てみると、相続人が活用に困る傾向にある田・畑は6件に1件、山林は20件に1件の割合です。
国も帰属後の活用を考慮してハードルを厳しくしていると思いますが、個人的にはもう少し要件の緩和をしてほしいところです。
- [2024.06.14]
- 初めまして
令和5年12月より新しくよつば会計に入社しました。
水川です。
よろしくお願いいたします。
私は、税理士事務所に勤めるまでは、工場で作業員として働いていました。
所得税や消費税の申告は当たり前に知らず、年末調整も会社から配られる扶養控除申告書に判子を押して提出するだけで何をやっているかよくわかっていませんでした。
税理士の勉強や実務を通して知識はついてきましたが、覚えることが多すぎて、苦労しています。
少しづつでも成長できるよう努力していきたいと思います。
確定申告や、年末調整を義務教育で教えないのはなぜなのでしょうか。
- [2024.05.31]
- 広島スポーツ
広島スポーツが盛り上がっていますね!
ドラゴンフライズ優勝、カープ単独首位、サンフレッチェも好調です。
前評判は高くなかっただけに、見事な下克上。勝ちじゃけえ!
6月11日に広島で行われるサッカーW杯予選のチケットが取れたので応援に行ってきます。
すでに2次予選突破を決めているので消化試合にはなりますが、ハラハラすることなく観戦できそうです。
まだまだスポーツについて熱く語りたいところですが、お仕事の話も。
国税庁を装った詐欺メールが届いているようです。
「税金が○○円滞納となっているので、〇月〇日までに納税しないと、財産を差し押さえます」といった内容です。
メールの文章をよく見ると、日本では使われない漢字が使われていたりと、おかしな文章になっています。
国税庁からメールで納税を督促されることはありませんので、絶対に支払いなどされないようにお気を付けください。
よつば会計 井手野下
- [2024.05.24]
- 大阪の旅
税理士・1級FP技能士の手嶋です。

前回ブログ(R5.8)は実技試験の前でしたが、無事合格しました。
5月の中旬に久しぶりに大阪に行きました。そこで驚いたことが2つ。
1つ目。インバウンド(訪日客)の多さ。
広島も多いなーと思っていましたが、全くレベルの違う混雑ぶりに唖然としました。
難波から道頓堀に向かうアーケードは人・人・人。場所によっては、
人混みで前も見えないほどで、インバウンドの増加を実感しました。
2つ目。御堂筋:国道25号線の車線の数。
京都から大阪市内のホテルへ移動するときに、カーナビの指示通りに進んでいて、
交差点を左折したら、知らないうちにものすごく広い片側8車線の一方通行を走っていました。
あとから調べたらここが御堂筋:国道25号線で車線数日本一の道路みたいです。
あまりの道路の広さに車線を数えたりしていると、カーナビの次の指示は右折!!!
えっ、うそでしょ?! ここで?!
内心かなりうろたえましたが、家族には平静を装いつつ、少しずつ車線変更を繰り返し、
何とか一番右側までたどり着きました。
が、しかし今度は右折場所がわからず通り過ぎる失態!!
街路樹の向こうに分離帯があり、そこを通行して右折するようでしたが、よくわからずじまい・・・。
ずいぶん先まで進んでから引き返すことになりました。
大阪市民の皆さんはよく運転しているなと感心します。本当に。
もう大阪市内は運転したくないですねー。心臓にわるいです^^
とは言え、旅は良いですね。日常にない刺激があって、楽しかったです。
- [2024.05.23]
- 【インボイス制度】 少額特例
令和5年10月よりインボイス制度がスタートし、事務処理等の混乱も少し落ち着いてきたと思いますが、【少額特例】のおさらい。
『一定規模以下の事業者』は、インボイス制度開始から『6年間』、『税込1万円未満』の課税仕入について、『インボイスの保存がなくても』、帳簿のみで『仕入税額控除が可能』。
注)一定規模以下の事業者とは・・・
①基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1億円以下
又は、
②特定期間(個人の場合は前年の1月から6月の期間、法人の場合は前事業年度開始の日から6月の期間)の課税売上高 が5千万円以下
今一度検討すると、この少額特例が適用できて事務負担を減らすことができるかもしれません。
- [2024.04.30]
- 国税の納付書が届かなくなる?なおはなし
令和6年5月送付分から「納付書」の送付対象者が見直されます。
理由は社会全体の効率化と行政コスト抑制だそうです。
電子申告とキャッシュレス納付を推進していますから、ふむふむ。理解できます。
国税庁によると対象は以下の通り
・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- 振替納税
- インターネットバンキング等による納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
e-Taxを利用している場合や、すでに紙の納付書を利用していない場合は事前送付の対象外になるみたいですね。
e-Taxで申告して紙の納付書を利用している場合などは令和6年5月送付分からは国税分は送付されてこないので注意が必要です。
ただし、源泉所得税の納付書や消費税の中間申告に係る納付書は、引き続き送付される予定とのことです。今のところ...
今後の納付方法について
①所轄税務署で白紙の納付書をもらい納付する
②キャッシュレス納付
キャッシュレス納付とは上記●で記載してある5項目になります。
ダイレクト納付と振替納税については事前申込が必要で、利用開始までに時間を要しますので注意が必要です。
これを機会にキャッシュレス納付を利用してみるのもいいかもしれませんね。
- [2024.04.22]
- しまなみ海道
穀雨の候、生命力豊かな季節となりました。
ルンルン陽気に背中を押され、「しまなみサイクリングロード」を走ってきました。
家族皆でのサイクリングのため、ゆっくりと多々羅しまなみ公園(愛媛県)で折り返し。
瀬戸田で一泊をはさみ、往復100㎞超の旅でした。
心地よい潮風、瀬戸内の絶景!
ストレス解消、無駄な脂肪も減少!
今度は今治までと考える今日この頃です。

瀬戸内といえば柑橘ですね。

橋を渡ると眼下には絶景が広がります。

自転車を止めて。レンタサイクルです。画面左上は桜。右は多々羅大橋です。
春のしまなみ、いい思い出になりました。
(大嶋)
- [2024.04.04]
- 定額減税
令和6年6月より定額減税が始まります。
令和6年分に限り所得税3万円・住民税1万円の合計4万円が減税となり、扶養の数に応じて減税額が増加します。
例)本人、配偶者、子の3人家族で、配偶者と子の所得が48万円以下である場合
4万円×3人=12万円減税(所得税9万円・住民税3万円)
サラリーマンの方は、6月以降の給料から天引きされる源泉所得税および住民税の金額が減税され、手取り金額が増加します。
個人事業主の方は、所得税は第1期予定納税分から控除、住民税は第1期分納税額から控除されます。
(個人事業主の場合、本人分(4万円)の減税は予定納税等の際に控除されますが、扶養分の減税は確定申告の際に控除されます)
また、年間の所得税・住民税の金額が定額減税の金額よりも少ない場合(定額減税の減税メリットが一部受けられない場合)は、減税の代わりにお住まいの市区町村より金銭が給付される予定です。
※令和6年分の所得金額が1,805万円超の方は定額減税が受けられない等、一定の条件がありますのでご注意ください。
- 2025年4月(1)
- 2025年1月(1)
- 2024年12月(4)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(4)
- 2024年9月(3)
- 2024年8月(4)
- 2024年7月(3)
- 2024年6月(2)
- 2024年5月(3)
- 2024年4月(3)
- 2023年12月(4)
- 2023年11月(3)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(2)
- 2023年8月(4)
- 2023年7月(3)
- 2023年6月(3)
- 2023年5月(3)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(1)
- 2023年1月(1)
- 2022年12月(5)
- 2022年11月(3)
- 2022年10月(2)
- 2022年9月(2)
- 2022年8月(4)
- 2022年7月(5)
- 2022年6月(4)
- 2022年5月(3)
- 2022年4月(2)
- 2022年3月(1)
- 2022年1月(3)
- 2021年12月(4)
- 2021年11月(2)
- 2021年10月(4)
- 2021年9月(2)
- 2021年8月(5)
- 2021年7月(2)
- 2021年6月(4)
- 2021年5月(3)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(1)
- 2020年12月(4)
- 2020年11月(2)
- 2020年10月(1)
- 2020年9月(3)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(4)
- 2020年5月(4)
- 2020年4月(2)
- 2020年3月(1)
- 2020年2月(1)
- 2020年1月(3)
- 2019年12月(5)
- 2019年11月(2)
- 2019年10月(3)
- 2019年9月(5)
- 2019年8月(4)
- 2019年7月(3)
- 2019年6月(3)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(4)
- 2019年3月(1)
- 2019年2月(1)
- 2019年1月(1)
- 2018年12月(3)
- 2018年11月(2)
- 2018年10月(4)
- 2018年9月(2)
- 2018年8月(5)
- 2018年7月(4)
- 2018年6月(6)
- 2018年5月(2)
- 2018年4月(2)
- 2018年3月(1)
- 2018年2月(1)
- 2018年1月(4)
- 2017年12月(3)
- 2017年11月(2)
- 2017年10月(2)
- 2017年9月(3)
- 2017年8月(2)
- 2017年7月(2)
- 2017年6月(2)
- 2017年5月(2)
- 2017年4月(2)
- 2017年3月(2)
- 2017年2月(2)
- 2017年1月(2)
- 2016年12月(4)
- 2016年11月(2)
- 2016年10月(2)
- 2016年9月(2)
- 2016年8月(4)
- 2016年7月(2)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(1)
- 2016年3月(1)
- 2016年2月(1)
- 2016年1月(2)
- 2015年11月(3)
- 2015年10月(3)
- 2015年9月(3)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(2)
- 2015年6月(4)
- 2015年5月(2)
- 2015年4月(3)
- 2015年3月(2)
- 2015年2月(2)
- 2015年1月(4)
- 2014年12月(3)
- 2014年11月(1)
- 2014年10月(3)
- 2014年9月(2)
- 2014年8月(3)
- 2014年7月(1)
- 2014年6月(2)
- 2014年5月(1)
- 2014年4月(2)
- 2014年3月(3)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(1)
- 2013年12月(2)
- 2013年11月(3)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(7)
- 2013年7月(9)
- 2013年6月(6)
- 2013年5月(4)
- 2013年4月(5)
- 2013年3月(7)
- 2013年2月(2)
- 2013年1月(4)
- 2012年12月(4)
- 2012年11月(5)
- 2012年10月(8)
- 2012年9月(8)
- 2012年8月(4)
- 2012年7月(6)
- 2012年6月(2)
- 2012年5月(1)
- 2012年4月(1)
- 2012年3月(2)
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(1)
- 2011年12月(1)
- 2011年11月(1)
- 2011年10月(1)
- 2011年8月(2)
- 2011年1月(1)
- 2010年11月(1)