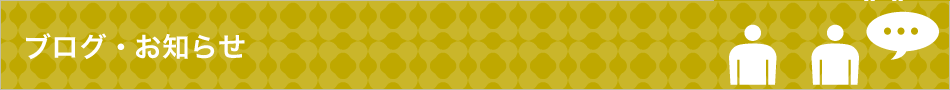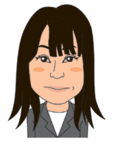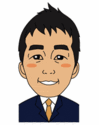- [2013.06.13]
- 事業年度って適当に決めていいの?
税理士の手嶋です。

本日のお題は会社の事業年度についてです。
事業年度は原則として会社の任意で定めることができます。
そして事業年度は1年を超えても問題ありませんが、法人税や消費税は1年を超える事業年度を
認めていないため通常は1年を単位に事業年度を設定しています。
平たく言うと、1年に1回は税金を計算して納税して下さいってことです。
1年を超える事業年度を設定できる必要があるのかという疑問は置いといて、
では何の制約もない場合にどうやって事業年度を決めるべきなのでしょう。
商売には少なからず季節変動というものがあります。
例えば3月の年度末に大きな利益が計上される場合には、この時期が上半期にくるように
事業年度を設定するのが良いのです。
なぜなら上半期にすることで、利益が予想以上に多かった場合には節税について
考えることができ、逆に利益が予想より少なかった場合には下半期の営業について
戦略を練り直すといった手を打つことができるからです。
これが3月決算の会社の場合には、利益が多いときはそれに対処できるわけもなく
その分納税が増え、利益が少ないときはそのまま赤字決算になることも考えられます。
3月が終わってからの出たとこ勝負になるため、これでは予定が立ちません。
事業年度の変更は株主総会を開催して定款を変更すれば簡単にできます。
上記のような場合には変更を考えてみてはいかがでしょうか。
ただし税理士は2月と3月は個人の確定申告で忙しいから、
できるだけ12月決算と1月決算はやめてほしいと思っています・・・。
- [2013.06.06]
- 養子縁組について④
税理士の手嶋です。

今回も養子縁組についてです。
養子縁組をすると名前が変わる場合があります。
これがネックで養子縁組をためらう方もいます。
戸籍の動きでいうと、養子縁組をすると養子は実親の戸籍から、養親の戸籍に移ります。
養親の籍に入ることにより養親の氏に変わります
ではすでに結婚している夫婦の場合はどうでしょう。
夫が養子になった場合と妻が養子になった場合と取り扱いは同じでしょうか?
夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称します。この規定は婚姻後も引き続き有効になります。
よって夫の氏を選択している次のような取扱いになります。
夫が養子になった場合・・・夫の氏も妻の氏も変わります。
妻が養子になった場合・・・妻の氏も夫の氏も変わりません。
妻だけ氏が変われば夫婦別姓になってしまいます。
養子縁組による親子関係よりも婚姻関係を重視しているためです。
そういえば、学生のころ苗字が変わった同級生がいたけどどんな事情だったのかな。
何にせよ名前が変わるっていうのは大きいですね。
養子縁組シリーズは今回で終了です。
- [2013.06.05]
- 祝!ワールドカップ出場決定
昨夜は、かなりの日本人が、サッカーを観戦していたのではないでしょうか?
日本代表とオーストラリア代表との一戦。1対1の引き分けではありましたが、ワールドカップへの出場が決まりました。
これで、5大会連続5回目の出場。「ドーハの悲劇」を知る世代としては、日本のサッカーもここまできたものだと感慨深いものがあります。
私も昨日の試合はテレビで観戦していましたが、特筆すべきは「本田圭佑」のプロ意識。1点差で負けていた後半ロスタイム。あそこで本田のはなった一撃。その後の雄叫び!そして、PK~同点ゴール
状態も万全ではない本田選手が、あの場面で強い信念を持って戦っていけるのは、その強いメンタル所以と言われます。
以前みたテレビ番組で本田選手は、
「いかに自分を信じてやれるか。未来を信じてやれるか。自分が絶対に成功するんだっていうことを自分に言い聞かせながら、自分の力を信じる。そうしたら必ず神様はそれを見ているし、神様からのビックサプライズを期待して頑張るだけ。」
と語っていました。
「自分を信じる」と簡単に言いますが、それだけの努力を積み重ねていないと自分を信じることはなかなかできないですよね。
税理士受験生の私ですが、今年の受験は断念しました あれやこれや言い訳はあるのですが、神様からのビックサプライズを期待して、自分の力を信じられるよう、来年に向けて始動します。
あれやこれや言い訳はあるのですが、神様からのビックサプライズを期待して、自分の力を信じられるよう、来年に向けて始動します。
(森下)
- [2013.05.31]
- 養子縁組について③
税理士の手嶋です。

今回も養子縁組についてです。
養子縁組は通常、養父・養母の双方と縁組をします。
養父のみあるいは養母のみの場合には、もう一方の同意が必要になります。
では一方が認知症で意思表示をできない場合にはどうすればよいのでしょうか?
養子縁組はできないのでしょうか?
民法では次のように規定しています。
第796条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
ただし書きにおいて、意思表示ができない場合には同意を得ることなく養父又は養母のみで縁組ができることになっています。
ちなみに役所の戸籍係に提出する養子縁組届には「配偶者が病気により、この縁組について同意の意思表示をすることができない」旨の記載をすることになります。
養子縁組の手続きは簡単ですが、軽々しくできることではありませんので慎重な判断が必要です。
また、進め方を間違えると相続人間で争いになることもあります。
やはりポイントは関係者には事前に説明することです。
後々トラブルにならないよう十分に注意して行いましょう。
- [2013.05.22]
- 養子縁組について②
税理士の手嶋です。

前回に引き続き養子縁組です。今回は養子の数の制限についてです。
民法上は養子の数に制限はありません。何人でも養子にできます。
ちなみに養子の数が増加すると、各相続人の相続分や遺留分割合は減少します。
相続税法も民法の相続人を基本としていますが、課税の公平の観点から民法とは異なる相続人の範囲を規定しています。
これはいまの相続税の計算方法は、相続人が多いほど税金が少なくなるからです。
相続税法上の養子の数の制限
① 実子がいる場合 ・・・養子の数は1人
② 実子がいない場合・・・養子の数は2人
養子の数の制限は、あくまでも相続税の計算上の問題だということです。
ただし自然な関係での養子縁組、連れ子を養子とした場合や特別養子の場合は、養子の数の制限はありません。
かつて10人以上と養子縁組をするなどの租税回避行為があったため、昭和63年の税制改正において上記の制限が設けられました。
何でもそうですが、やりすぎる人がいるとそれに対する規制ができるのですね。
次回も養子縁組についてです。しつこい?!
- [2013.05.14]
- 田植えの季節
5月5日に田植えが終わりました。
農業は先行き不透明ながら、収穫までは畦の草刈りに励まなくては。
5月提出(3月決算月)の法人税の申告に、復興特別所得税の別表が加わりました。源泉徴収されている復興特別所得税の集計が必要になり、一手間増えました。法人税は3年間で終わるから良しとしても、個人の所得税は平成49年までの25年間です。先の長い話となっています。
教育資金贈与をするためには、資金を一旦銀行等に預けなくてはなりません。信託会社・銀行等が「教育資金贈与信託」なる専用商品をだして、資金集めに動いているようです。
利用条件(払出条件・手数料・最低利用額等)がそれぞれで違うようですから、使い勝手を良く吟味する必要がありそうです。
とにかく、急ぎの相続税対策には、よさそうな制度です。
藤川
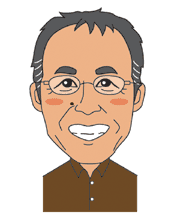
- [2013.05.10]
- 教育資金の贈与
税理士の檜山です。
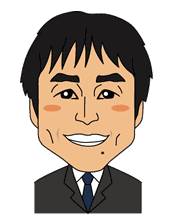
今シーズンの出場レースも残すは可部連山トレイルランの1つとなりました。5月は法人の決算業務が多い月なので、時間を見繕いながらトレーニングに励もうと思います。
さて、25年4月より教育資金贈与の非課税特例制度がスタートしました。いろんなところで詳細が取り上げられていますので、簡単な概要だけを最後に記載しました。
今回は、昔からある教育資金の非課税の規定についてです。
税法上、以前から子や孫に対する教育資金を贈与する際の非課税の規定が設けられています。
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものの価額は、贈与税の課税価額に算入しない」(相続税法21-3)
この規定を適用する場合の注意点は、「必要な都度直接」これらの用に充てるための贈与を行わなくてはいけません。まとめて1年分の教育費を贈与とする行為は「必要な都度直接」に該当しませんので、非課税の要件を満たさなくなります。
学校の授業料・塾代などの振替を祖父母口座にしておけば、「必要な都度直接」を満たしますので非課税となります。
教育資金に関しては、期間限定ですが2つの非課税規定ができたことになります。各家庭によってどちらが有利かどうか違ってきます。適用については、しっかり考えることが肝要です。
【教育資金贈与の非課税特例の概要】
平成25年4月から平成27年12月までの期間、父母や祖父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫に対して、教育等に係る費用を最大1500万円まで非課税とする制度です。学校の入学金や授業料その他学業に付随するものはもちろん、学習塾や野球・ピアノなどの習い事も対象となります。
手続きとしては、銀行や証券会社に子等の口座を設け、教育資金非課税申告書を税務署へ提出し、その口座へ資金を預ければOKです。その後、教育資金を支払した時の領収書を銀行等に提出し、銀行等から払い出しを受けるという流れです。
なお、贈与を受けた者が30歳に達した時口座に残額があった金額については、その時に贈与税が課税されます。
- [2013.04.26]
- クレジットカードを利用して治療費を支払う場合の税務
クレジットカード(以下「カード」)が普及して、今では治療費や入院費をカードで支払うことができる病医院が増えています。
患者側からすれば、ポイントを貯めることや持ち歩き現金を少なくするというメリットがあります。病医院側とすれば、一定の手数料を支払わなければならない一方で、未収金の軽減や手元現金を少なくできるメリットはあるといえます。
さて、このようなカードを利用した治療費の支払いについて、病医院側と患者側の税の取扱いはどのようになっているのでしょうか。
<病医院側の税の取扱い>
病医院側の取扱いは原則として次のとおりです。
(例)
①保険治療を行い、治療費2,000円を請求。カードで全額支払われた。
(借方)未収入金 2,000円 (貸方)窓口収入 2,000円
②信販会社から、加盟店手数料5%を差し引かれた残高1,900円が通帳へ入金された。
(借方)預金 1,900円 (貸方)未収入金 2,000円
支払手数料 100円
<患者側の税の取扱い>
- 医療費控除の対象金額
患者側の税の取扱いは、まず上記例の治療費2,000円が医療費控除の対象となります。分割で信販会社に支払ったことによる金利や手数料は、医療費控除の対象となりません。これは、患者と信販会社との問題であって、治療とは何ら関係がないためです。
- いつの時点で医療費控除の対象となるか
カードによって治療費を支払った日が医療費控除の対象となる支払日になります。つまり、クレジット契約が成立した時です。
このように病医院でのカード払いについて、いつの時点で医療費控除の対象になるか、患者の関心は大いにあるでしょう。カード払いを導入される場合は、窓口などで説明する資料を用意するといいかもしれません。
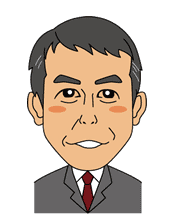
(錦織)
- [2013.04.22]
- 養子縁組について①
税理士の手嶋です。
平成27年度の税制改正ではありますが、相続税の基礎控除の縮減がとうとう決まりました。
特に都市部において、影響が大きいですね。
多くの雑誌で特集が組まれ、世の中の相続に対する関心が高まってきているのを感じます。
そんな流れに乗って、相続とは関係が深い、養子縁組に触れてみます。
今回は養子縁組をした場合の実親及び養親との親子関係について解説します。
養子は養子縁組をすると養父・養母と新たに親子関係を有することになります
これは法律によってできた血族関係であり、法定血族と言われます。
では実の両親との親子関係はどうなるのでしょうか?
普通養子縁組では実の両親との親子関係がなくなることはありません。
こちらは血のつながった血族関係であり、自然血族です。
(※特別養子縁組の場合は、親子関係はなくなります。)
ですから普通養子縁組をすると法定血族、自然血族といった違いはありますが、
2重の親子関係となり実親と養親の相続権を有することになります。
- [2013.04.13]
- ホームページをスマホに対応
詳しい事は分かりませんが、どうやら携帯電話やスマホで当ホームページを開くと、一部がきちんと表示できなかったようです。
そこでこの度、きちんと表示されるよう、手を加えて頂きました。
これにより、例えば喫茶店でコーヒーを飲みながら・・・または待ち合わせで待たされながら・・・そして時には浜辺で海を感じながら・・・・・ホームページをご覧頂けます。
しかし道を歩きながらはいけません。危険なので問題になっているそうです。
あとはきちんと表示されるに値するきちんとした記事を書くだけ。
それでは失礼します。
(中田裕介)
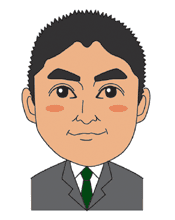
- 2025年4月(1)
- 2025年1月(1)
- 2024年12月(4)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(4)
- 2024年9月(3)
- 2024年8月(4)
- 2024年7月(3)
- 2024年6月(2)
- 2024年5月(3)
- 2024年4月(3)
- 2023年12月(4)
- 2023年11月(3)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(2)
- 2023年8月(4)
- 2023年7月(3)
- 2023年6月(3)
- 2023年5月(3)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(1)
- 2023年1月(1)
- 2022年12月(5)
- 2022年11月(3)
- 2022年10月(2)
- 2022年9月(2)
- 2022年8月(4)
- 2022年7月(5)
- 2022年6月(4)
- 2022年5月(3)
- 2022年4月(2)
- 2022年3月(1)
- 2022年1月(3)
- 2021年12月(4)
- 2021年11月(2)
- 2021年10月(4)
- 2021年9月(2)
- 2021年8月(5)
- 2021年7月(2)
- 2021年6月(4)
- 2021年5月(3)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(1)
- 2020年12月(4)
- 2020年11月(2)
- 2020年10月(1)
- 2020年9月(3)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(4)
- 2020年5月(4)
- 2020年4月(2)
- 2020年3月(1)
- 2020年2月(1)
- 2020年1月(3)
- 2019年12月(5)
- 2019年11月(2)
- 2019年10月(3)
- 2019年9月(5)
- 2019年8月(4)
- 2019年7月(3)
- 2019年6月(3)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(4)
- 2019年3月(1)
- 2019年2月(1)
- 2019年1月(1)
- 2018年12月(3)
- 2018年11月(2)
- 2018年10月(4)
- 2018年9月(2)
- 2018年8月(5)
- 2018年7月(4)
- 2018年6月(6)
- 2018年5月(2)
- 2018年4月(2)
- 2018年3月(1)
- 2018年2月(1)
- 2018年1月(4)
- 2017年12月(3)
- 2017年11月(2)
- 2017年10月(2)
- 2017年9月(3)
- 2017年8月(2)
- 2017年7月(2)
- 2017年6月(2)
- 2017年5月(2)
- 2017年4月(2)
- 2017年3月(2)
- 2017年2月(2)
- 2017年1月(2)
- 2016年12月(4)
- 2016年11月(2)
- 2016年10月(2)
- 2016年9月(2)
- 2016年8月(4)
- 2016年7月(2)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(1)
- 2016年3月(1)
- 2016年2月(1)
- 2016年1月(2)
- 2015年11月(3)
- 2015年10月(3)
- 2015年9月(3)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(2)
- 2015年6月(4)
- 2015年5月(2)
- 2015年4月(3)
- 2015年3月(2)
- 2015年2月(2)
- 2015年1月(4)
- 2014年12月(3)
- 2014年11月(1)
- 2014年10月(3)
- 2014年9月(2)
- 2014年8月(3)
- 2014年7月(1)
- 2014年6月(2)
- 2014年5月(1)
- 2014年4月(2)
- 2014年3月(3)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(1)
- 2013年12月(2)
- 2013年11月(3)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(7)
- 2013年7月(9)
- 2013年6月(6)
- 2013年5月(4)
- 2013年4月(5)
- 2013年3月(7)
- 2013年2月(2)
- 2013年1月(4)
- 2012年12月(4)
- 2012年11月(5)
- 2012年10月(8)
- 2012年9月(8)
- 2012年8月(4)
- 2012年7月(6)
- 2012年6月(2)
- 2012年5月(1)
- 2012年4月(1)
- 2012年3月(2)
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(1)
- 2011年12月(1)
- 2011年11月(1)
- 2011年10月(1)
- 2011年8月(2)
- 2011年1月(1)
- 2010年11月(1)