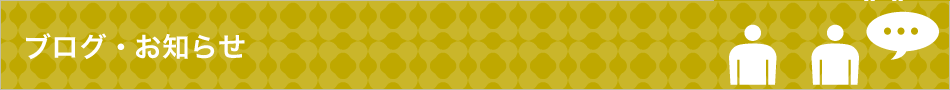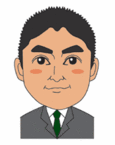- [2013.02.18]
- 難しいことをやさしく
税理士の手嶋です。

今日から確定申告の受付が始まりました。
うちの事務所はおかげさまで件数が多いのですが、その分取り掛かりも早く1月下旬からせっせと作成しており、順調に進んでいるようです。
そんな合間に、先週、広島西倫理法人会でセミナーをさせていただきました。
モーニングセミナーは毎週行われているようで、なんとスタートは朝6時。
できる経営者の朝は早いのですね。
セミナーの内容は、資金会計理論という財務諸表を資金の面から分析する考え方を用いて、貸借対照表を棒グラフと折れ線グラフで表してみるといったものでした。
わかりにくい貸借対照表もビジュアル化することで、それまで気づかなかったことが見えてきます。
良い会社のグラフ、悪い会社のグラフと、話題のPanasonic、SHARPの財務分析などもしてみました。
セミナー後の朝食会では、参加者から「わかりやすかった」というありがたい言葉をいただきましたが、「会計って難しいね」との感想もいただきました。
難しいことをやさしく、
やさしいことを深く、
深いことを面白く
と心がけていますが、これがなかなか容易ではないですね。
知っていることをわかりやすく伝える。
そういえば池上彰さんはどんなテクニックを使っているのか気になります。
早速、検索すると、「伝える技術」とか「伝える力」とか出てきました。
結構、たくさんあります。池上さん商売上手です。
レビューの評価高いので、ちょっと一冊読んでみます。
- [2013.01.30]
- 25年度税制改正大綱
税理士の檜山です。
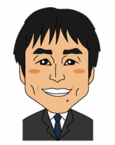
年明けから寒さと仕事でなかなか走れず、市民ランナーと名乗れなくなりつつあります。
すぐに身体がなまってしまうので時間を見つけて走りたいと思います。
さて、先週25年度の税制改正大綱が発表されました。今回の大綱については、波乱なく可決される見込みのようです。
26年4月・27年10月の消費税率の引き上げがあるため、低所得者の負担が増加します。それの不公平感を解消するためか、今回の大綱は個人の高所得者の課税強化が色濃く感じます。
また、海外諸国との競争力強化・景気の底入れ・雇用の確保の観点から法人については税額控除や所得控除が拡充しています。
なお、主だったポイントは以下のとおりです。
・【法人税】試験研究費や投資促進税制の税額控除の新設・拡大
・【法人税】中小企業の交際費枠を年800万円まで全額損金算入
・【所得税】最高税率が45%に引き上げ
・【所得税】2014年4月~2017年12月の住宅ローン控除の最高控除額が年40万円
・【相続税】最高税率が55%に引き上げ
・【贈与税】孫への教育資金1500万円を限度に非課税
・【自動車取得税】2014年4月に縮小、2015年10月廃止
- [2013.01.19]
- 税務署から届く書類
よつば会計 森下です。
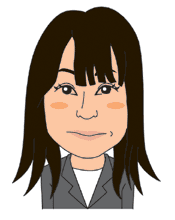
やっとのことでお正月気分が抜けたと思う今日この頃。
すでに1月も後半になっていますね。
ふと気づけば、今年も確定申告の時期がやってきます。
お客様に確定申告のお知らせをしていますが、お客様から「毎年税務署からくる大きい封筒が来たらまた連絡するからね!」と言われることが多々あります。
ここで注意です![]()
よつば会計では、昨年から電子申告を本格的に行っています。
昨年電子申告した方には、今年は税務署から「申告書等(大きい封筒)」は届きません。
もちろん、税務署から書類などが届かないからと言って、申告しなくてよいというわけではありませんので、ご注意を!
また、昨年紙で提出した方には、例年通り税務署から「申告書等(大きい封筒)」が届きます。
例年税務署から届く申告書等には、たくさんのパンフレットや冊子が入っていますよね。
電子申告が主流になり、申告書等の紙媒体を送付しなくなると、税務署側は経費削減になるしエコにもつながっていくような気もします。
けれど、やはりあの大きい封筒がないと「確定申告だ!」という実感がわかず、ちょっとさみしい気がするのは私だけでしょうか?
- [2013.01.13]
- お守りと消費税
税理士の檜山です。
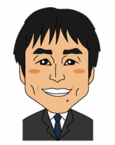
平成25年もはじまって2週間ばかり過ぎました。年末年始に食べ過ぎたのもあって、今年はランニング生活のスタートは遅めです。
今年も元気に一年を過ごせるように、3日に近くの神社へ初詣に行ってきました。毎年同様、昨年お世話になったお守りを奉納し、お参りをしておみくじをひいてお守りを買って帰りました。
お守りといえば、以前月次監査でお邪魔したクライアントの経理の方からこんな質問を受けました。
「会社が神社でお守りやお札を購入した場合、消費税はかかっているんですよね?」
結論から言うと消費税は課税されません。
そもそも消費税が課税される取引は、以下の4つの要件を満たすものとされています。
- 国内で行われること
- 事業者が事業として行うこと
- 対価を得て行われること
- 資産の譲渡、資産の貸付け、役務提供のいずれかであること
上の要件を一読すると、消費税が課税される取引に見えます。しかし、法人税法の基本通達において「宗教法人のお守り等の販売は、売価と仕入原価の関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする」と規定しており、事業性および対価性の観点から課税要件を満たさないと解されます。
おみくじについても同様な考えです。今年の私のおみくじは末吉でした。旅行の項目は良かったので、今年はもう少し県外のマラソン大会に行きたいものです。
- [2013.01.05]
- あけましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。
みなさまにとって素敵な年となりますことを、お祈りいたします。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の檜山です。
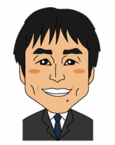
年末休暇を利用して白木山に登ってきました。道のりとしては3km少々と短いものの高低差800mに加え5合目からは雪が積もっており足を取られ滑りながらも上を目指しました。12月のなまった身体には堪える山登りでした。かれこれ1時間少々で頂上にたどり着きましたが、息は上がり両ひざはすでに張った状態で満身創痍。
しかし、苦労した甲斐もあり山頂からの眺めは絶景、そして24年を静かに振り返る時間を持つことができました。
この絶景・時間と引き換えに次の日から数日間、筋肉痛に苦しみましたが実りあるものとなりました。
さて、会計事務所にとっては、1月は支給後の年末調整・法定調書・総括表・償却資産の作成・提出があり、2月から3月半ばまでは所得税の確定申告と繁忙期に突入します。
毎年のことながら、忙しく目が回ると思いますが、段取り・計画をしっかり組立て実行していけるよう頑張ります。
- [2012.12.29]
- 年末年始のお知らせ
税理士の檜山です。
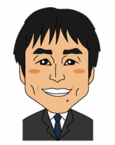
早いもので平成24年も残すところ、今日を含め3日となりました。
会社の営業は昨日をもって、年末年始の休暇に入らせていただきます。
年明けは1月5日より再開いたします。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
- [2012.12.21]
- 職員第一
今年もあともう少し。この12月はインフルエンザが流行らなかったですね。1月か2月に流行しそうな気がします。冬は何かと病院にかかることが多い季節です。私のクライアントに病院・診療所が結構あります。その関係で医療経営の勉強もしています。その中で面白いなと思ったことに、「職員第一」という考え方があります。一般企業で「顧客第一」ということはよく聞きます。それが医療経営では「職員第一」なのです。
風邪等で診療所にかかるとき、診療所に入って、受付して、待合室で待って、看護師さんの問診を受けて、ドクターに診てもらって、その後また看護師さんに処置等をしてもらって、受付で薬(又は処方箋)をもらって、会計を済ませて、診療所を出る、という一連の流れ、時間の中で、ドクターに接するのは実はほんのわずかな時間なのです。ドクターの適切な診察、処置はもちろん重要ですが、患者がその診療所を評価するウェイトは、ドクターよりも接する機会の多い受付や看護師などのスタッフの接遇が大きいと言われています。そのスタッフが、「うちのドクターは素晴らしい。この診療所も好き。ここで働けて幸せ。」と思って患者に接するのと、その反対を思って接するのでは、診療所に対する患者の印象が随分違ってくるのです。いくらドクターが素晴らしくても、ドクターより接する機会の多いスタッフの素晴らしさの方が患者の好感度を上げるようです。だから、ドクターはスタッフを一番に大事にしなさい、ということです。
この「職員第一」という考え方は一般企業でも参考になることだと思います。ただし、職員が「職員第一」を勘違いしてしまうと大変なことになるので、注意が必要です。
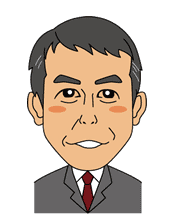
(錦織)
- [2012.12.10]
- 自筆証書遺言と公正証書遺言
税理士の檜山です。
相続が発生した場合、実務家として最初に確認することは遺言があるかどうかです。
遺言として一般的に知られているものは自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがあり、各々についてそれぞれ長所・短所があります。
自筆遺言証書は字のごとく、遺言者本人が自筆で全文・年月日・氏名を書くことが要件となっています。自らが行うものですので、費用もほとんどかかりません。また、何度でも書き直せるため気軽に作成できます。 しかし、記載方法を誤ると内容自体が無効となることもあり、紛失する恐れなどリスクをはらんでいることも多々あります。さらに、その遺言が本人が書いたものかどうか、裁判所で検認する必要があります。
一方、公正証書遺言は、公証人によって公正証書として遺言が作成され、内容等に不備がチェックされますので書類が無効となることはありません。また、公証人役場に原本が保管されるため紛失等のリスクはありません。しかし、公証人と打合せや費用がかかるなど、手間とお金がかかります。
将来のことを考え遺言を遺そうとお考えの方には、手間とお金がかかりますが、公正証書遺言をお勧めいたします。
- [2012.12.04]
- 大掃除しました。
今年もついに12月。毎年思う「あー、はやい。」
そして今日は会社の大掃除。「あー、だるい。」
うそ、だるくない。
机の中をせっせと片づけていたら、ポケットティッシュがいっぱい出てきた。
なぜだ・・・!!
何も考えなくても貯まるポケットティッシュ。
考えないと貯まらないお金。
しかし、来年は貯まるのだ。なぜなら、かなり前に家出してしまいずっと探していた彼が、机の引き出しの最深部から見つかったからだ。
数年前にどこかの神社のおみくじに入っていた彼。ずっと私の財布に住んでいた。
よっし!年が明ける前に見つかった!!
ズタボロやん。一体何があったん。
絶対来年も貯まらん。。。
(中田裕介)
- [2012.11.19]
- 不動産所得の節税のための法人活用(その1)
不動産所得の節税のための法人活用は3タイプあります。
(1)土地建物は個人所有のまま、管理を法人が行い、個人が法人に管理手数料を支払うタイプ
(2)土地建物は個人所有のまま、建物を法人が一括で借上げるタイプ
(3)土地は個人所有で建物が法人所有のタイプ
所得税の節税が大きく見込めるのは(3)の建物を法人所有とするタイプです。
しかし、相続対策として建設するアパートやマンションなどは、個人名義でなければなりません。
高収益が見込める店舗や事務所倉庫系の物件は、法人名義で建設するほうが有利です。
アパートやマンション、戸建借家などは築後20~30年経過して建設時の借入金を支払い終わったころが法人化活用が可能となります。
法人に建物を売却することによって、家賃収入をまるまる法人へ移転することができます。
法人を最も有効に活用するための考え方や、相続税に対する影響などについては次回ご紹介しましょう。
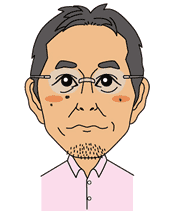
中 田
- 2025年4月(1)
- 2025年1月(1)
- 2024年12月(4)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(4)
- 2024年9月(3)
- 2024年8月(4)
- 2024年7月(3)
- 2024年6月(2)
- 2024年5月(3)
- 2024年4月(3)
- 2023年12月(4)
- 2023年11月(3)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(2)
- 2023年8月(4)
- 2023年7月(3)
- 2023年6月(3)
- 2023年5月(3)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(1)
- 2023年1月(1)
- 2022年12月(5)
- 2022年11月(3)
- 2022年10月(2)
- 2022年9月(2)
- 2022年8月(4)
- 2022年7月(5)
- 2022年6月(4)
- 2022年5月(3)
- 2022年4月(2)
- 2022年3月(1)
- 2022年1月(3)
- 2021年12月(4)
- 2021年11月(2)
- 2021年10月(4)
- 2021年9月(2)
- 2021年8月(5)
- 2021年7月(2)
- 2021年6月(4)
- 2021年5月(3)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(1)
- 2020年12月(4)
- 2020年11月(2)
- 2020年10月(1)
- 2020年9月(3)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(4)
- 2020年5月(4)
- 2020年4月(2)
- 2020年3月(1)
- 2020年2月(1)
- 2020年1月(3)
- 2019年12月(5)
- 2019年11月(2)
- 2019年10月(3)
- 2019年9月(5)
- 2019年8月(4)
- 2019年7月(3)
- 2019年6月(3)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(4)
- 2019年3月(1)
- 2019年2月(1)
- 2019年1月(1)
- 2018年12月(3)
- 2018年11月(2)
- 2018年10月(4)
- 2018年9月(2)
- 2018年8月(5)
- 2018年7月(4)
- 2018年6月(6)
- 2018年5月(2)
- 2018年4月(2)
- 2018年3月(1)
- 2018年2月(1)
- 2018年1月(4)
- 2017年12月(3)
- 2017年11月(2)
- 2017年10月(2)
- 2017年9月(3)
- 2017年8月(2)
- 2017年7月(2)
- 2017年6月(2)
- 2017年5月(2)
- 2017年4月(2)
- 2017年3月(2)
- 2017年2月(2)
- 2017年1月(2)
- 2016年12月(4)
- 2016年11月(2)
- 2016年10月(2)
- 2016年9月(2)
- 2016年8月(4)
- 2016年7月(2)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(1)
- 2016年3月(1)
- 2016年2月(1)
- 2016年1月(2)
- 2015年11月(3)
- 2015年10月(3)
- 2015年9月(3)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(2)
- 2015年6月(4)
- 2015年5月(2)
- 2015年4月(3)
- 2015年3月(2)
- 2015年2月(2)
- 2015年1月(4)
- 2014年12月(3)
- 2014年11月(1)
- 2014年10月(3)
- 2014年9月(2)
- 2014年8月(3)
- 2014年7月(1)
- 2014年6月(2)
- 2014年5月(1)
- 2014年4月(2)
- 2014年3月(3)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(1)
- 2013年12月(2)
- 2013年11月(3)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(7)
- 2013年7月(9)
- 2013年6月(6)
- 2013年5月(4)
- 2013年4月(5)
- 2013年3月(7)
- 2013年2月(2)
- 2013年1月(4)
- 2012年12月(4)
- 2012年11月(5)
- 2012年10月(8)
- 2012年9月(8)
- 2012年8月(4)
- 2012年7月(6)
- 2012年6月(2)
- 2012年5月(1)
- 2012年4月(1)
- 2012年3月(2)
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(1)
- 2011年12月(1)
- 2011年11月(1)
- 2011年10月(1)
- 2011年8月(2)
- 2011年1月(1)
- 2010年11月(1)